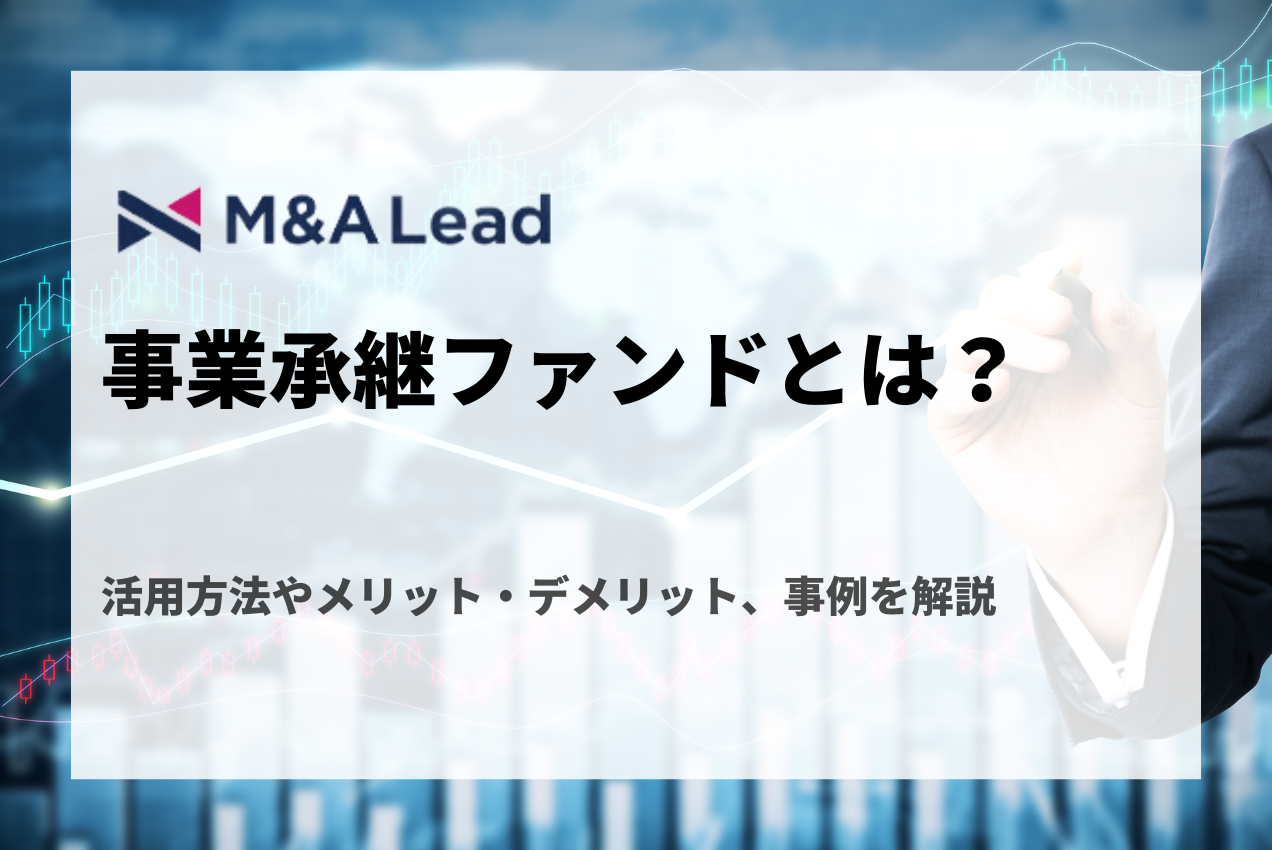
中小企業の経営者にとって、後継者問題は避けて通れない課題の一つです。特に親族や社内に後継候補がいない場合、事業の継続が難しくなり、廃業という選択肢も現実味を帯びてきます。
そこで注目を集めているのが「事業承継ファンド」の存在です。単なる買収にとどまらず、経営支援を通じて企業価値を高めながらバトンを渡す仕組みは、数多くの成功事例を生んでいます。
本記事では、事業承継ファンドの概要や選ぶ際のポイント、また実際に事業承継ファンドが活用された代表的な事例についても解説していきます。
この記事の監修者目次
中小企業における事業承継の手段として、近年注目されているのが「事業承継ファンド」です。
事業承継ファンドは、後継者が不在の企業に対して経営の引継ぎを支援することを目的とした投資ファンドであり、単なる資金援助ではなく、経営そのものに深く関与し、企業価値の向上を図る役割を担います。企業の持続的な発展を目指すうえで、事業承継ファンドは実に有効な選択肢の一つといえるでしょう。
ファンドとは、本来「資金」や「基金」を意味する言葉で、投資家から集めたお金を運用し、その利益を還元する仕組みです。事業承継ファンドはその一形態として、特に後継者不在に直面する中小企業の株式を取得し、経営権を得た上で、外部から人材を派遣しながら経営支援を行います。その後、企業価値を高めた段階でM&Aを通じて株式を売却し、得られた収益を投資家に分配するという構造になっています。
M&Aの基本的な概要については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。
→M&Aとは?概要・流れ・メリット・デメリット・成功ポイントを解説
一般的なファンドと事業承継ファンドの最大の違いは、投資先と関与の度合いにあります。一般のファンドが主に上場株式や債券などを対象に分散投資を行うのに対して、事業承継ファンドは中小企業、特に後継者不在の企業に集中して投資を行います。
さらに、一般のファンドは投資先企業の経営に直接関与しないのが一般的ですが、事業承継ファンドではオーナー経営者から株式を買い取り、経営権を得た上で、自ら経営支援に乗り出します。財務面だけでなく、人的資源の補強や業務改善にも踏み込んでサポートする点が、大きな特徴といえるでしょう。
事業承継の手法には大きく分けて「親族内承継」「社内承継」「第三者承継(M&A)」の三つがあります。親族内承継は子息や親族に経営を譲る形で、社内承継は従業員や役員が後を継ぐケースです。そして、第三者に承継する方法がM&Aですが、事業承継ファンドはこのM&Aの一形態と位置づけられます。
M&Aでは、企業やファンドなどが買い手として現れますが、事業承継ファンドの特長は、単に買収を行うだけでなく、継続的な経営支援を通じて企業の成長を促す点にあります。さらに、通常のM&Aが比較的短期的な成果やシナジー効果を重視するのに対し、事業承継ファンドは中長期的な視点で経営基盤の強化や文化の継承に重きを置くことが多く、売り手企業の価値観を尊重した支援を行う傾向にあります。
従業員への事業承継については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。 会社売却や事業承継など、M&Aに関するお悩みは、ぜひM&A Leadへご相談ください。 当社は「完全成功報酬制」を採用しており、譲渡が成立し譲渡対価が入金されるまでは一切料金をいただきません。お気軽にご相談いただけます。 また、知識・支援実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、ご相談からクロージングまで、売主様に徹底的に寄り添いサポートいたします。 さらに、当社のアドバイザーだけでなく、当社が運営するM&Aアドバイザー紹介プラットフォームにご登録いただいているM&Aアドバイザー様のネットワークも活用可能なので、どのような業界・業種の案件にもご対応可能です。 当社はこの強みをフルに活用して、M&Aをお考えのオーナー様に徹底的に寄り添い、売却成功までサポートいたします。 無料相談は随時お受けしておりますので、お電話・Webよりお気軽にお問い合わせください。
→従業員承継とは?メリット・デメリットや承継の流れを解説
事業承継ファンドは、単なる第三者承継手段にとどまらず、企業の抱える経営課題や資金問題を多角的に支援できる存在です。特に後継者不足や資金調達に悩む企業にとっては、柔軟で実用性の高い解決策となり得ます。ここでは、事業承継ファンドが有効に活用できる代表的なケースを紹介します。
後継者不在は多くの中小企業にとって深刻な課題です。親族や社内に後継候補が見つからない場合、企業存続の道は閉ざされかねません。こうした状況で有効なのが、事業承継ファンドの活用です。
事業承継ファンドに株式を売却すれば、経営権はファンド側へと移ります。ファンドはそれと同時に経営陣や人材を派遣し、事業を継続・成長させる体制を整えます。後継者探しに時間を割くことなく、スムーズにバトンタッチできるのが大きな利点です。
また、ファンド側は成長意欲のある外部人材を探し出し、育成するノウハウも持っているため、企業に合った後継体制の構築が可能です。
企業によっては後継者候補がいるものの、まだ経営を任せるには経験や実力が足りないという状況も少なくありません。このようなケースでも、事業承継ファンドは心強い味方となります。
一部の事業承継ファンドは、後継者育成にも注力しており、企業の実態に即した支援体制を構築できます。具体的には、ファンドから経営のプロフェッショナルを派遣して、後継者の実務能力や経営判断力の強化を図ることで、経営者の退任後も安定した体制で事業を継続できる環境を整えられます。
後継者が社内にいたとしても、株式の買い取りに必要な資金を自力で調達できない場合、事業承継が進まず宙に浮いてしまうことがあります。資金面の課題をクリアする手段としても、事業承継ファンドは有効です。
まず、現経営者が保有する株式をファンドへ売却し、資金を得ます。その後、後継者は企業の運営に従事しながら、段階的に資金を蓄積し、最終的にファンドから株式を買い戻すことで、正式な承継を完了させることができます。
資金不足の状態でも時間をかけて着実に承継が進められる点が、企業側にとっても後継者側にとっても大きなメリットです。
中には経営の現場を熟知している現経営陣に引き続き経営を任せたいと考える企業も少なくありません。
ファンドは株式を取得することで企業の経営基盤を支える一方、実際の経営は引き続き現経営陣が行うという形式も可能です。株主と経営者の役割を分離することで、創業者は引退後も安心して企業の今後を託せる体制が整います。
ファンド側は企業価値の向上を目的としており、経営の継続性が確保できる限り、現体制を尊重する傾向があります。
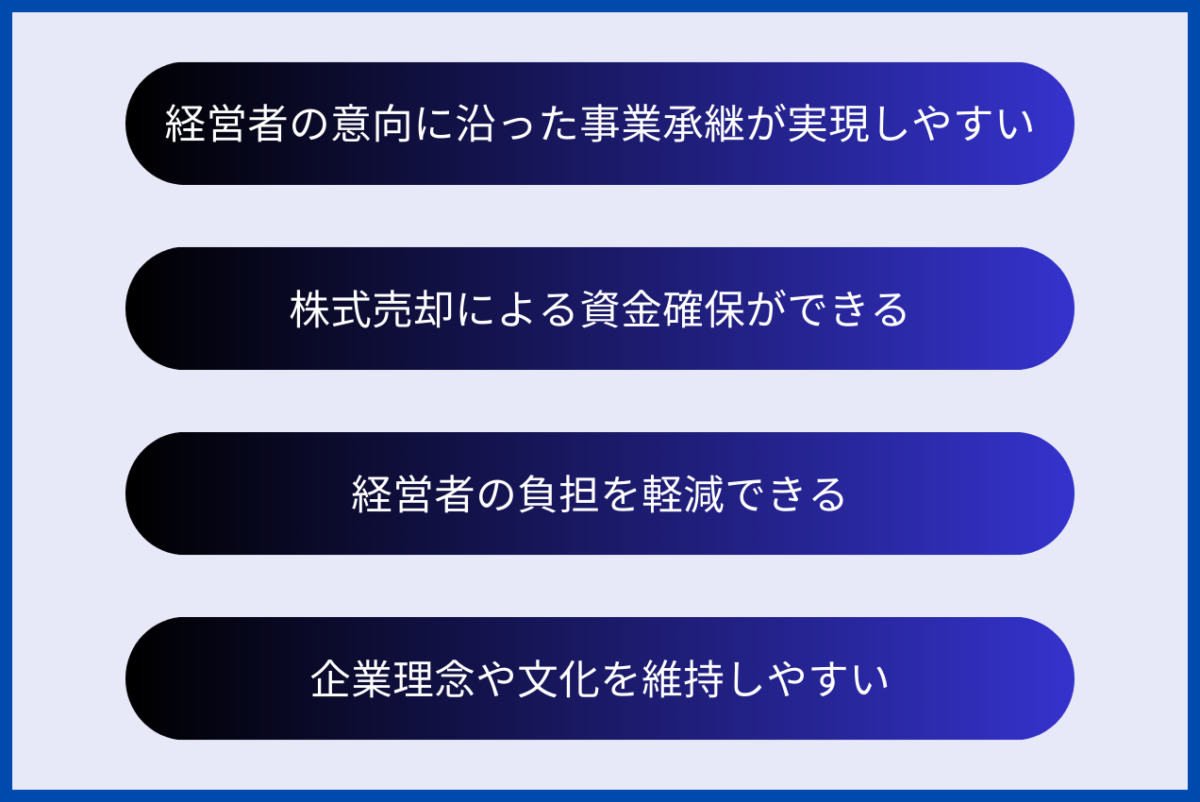
事業承継ファンドの活用には、単なる経営引継ぎにとどまらない多くの利点があります。後継者不在の解消や売却益の確保、さらには企業理念の承継など、中小企業の経営者が抱える課題を多角的にサポートしてくれる存在です。ここでは主なメリットを詳しく解説します。
事業承継ファンドの最大の魅力は、経営者が望む形での事業承継を実現しやすい点にあります。
ファンドは豊富なネットワークとノウハウを活かし、経営者の意向を汲み取ったうえで後継者の選定や育成を行ってくれます。社内に後継者がいない場合でも、外部から最適な人材を見つけてくる柔軟さがあるため、経営者の理想に近い形での承継が可能です。
理念や経営方針の承継まで見据えた事業承継が実現できる点は、他の承継手段にはない大きな利点といえます。
事業承継ファンドを活用すれば、経営者は自社の株式をファンドに売却することで、まとまった資金を得られます。売却益は、経営者自身の引退後の生活資金に充てるだけでなく、新たな事業に再挑戦するための資金源としても活用できます。
一般的なM&Aに比べ、契約交渉や手続きの手間が比較的少なく、スムーズに進めやすいという点も大きなメリットです。
経営を担ってきた経営者は、事業の承継だけでなく、資金繰りや人材確保など多くの課題を抱えています。事業承継ファンドは経営課題に対して、パートナーとして支援してくれる存在です。経営者が抱える精神的・実務的な負担を軽くし、安心して次の世代へのバトンタッチが行える環境を整えてくれます。
特に中小企業においては、経営者の一極集中体制になりがちなため、この支援は大きな意義を持ちます。
事業承継ファンドは、経営効率だけでなく企業の「らしさ」も尊重した支援を行う点が特徴です。
M&Aでは買い手企業の方針によって企業文化が変わってしまうことがありますが、事業承継ファンドは経営者の意向や社風を十分に理解し、それを壊さず承継していく姿勢を大切にしています。従業員や取引先にとっても、馴染みある環境が保たれることで不安や混乱を最小限に抑えることができます。
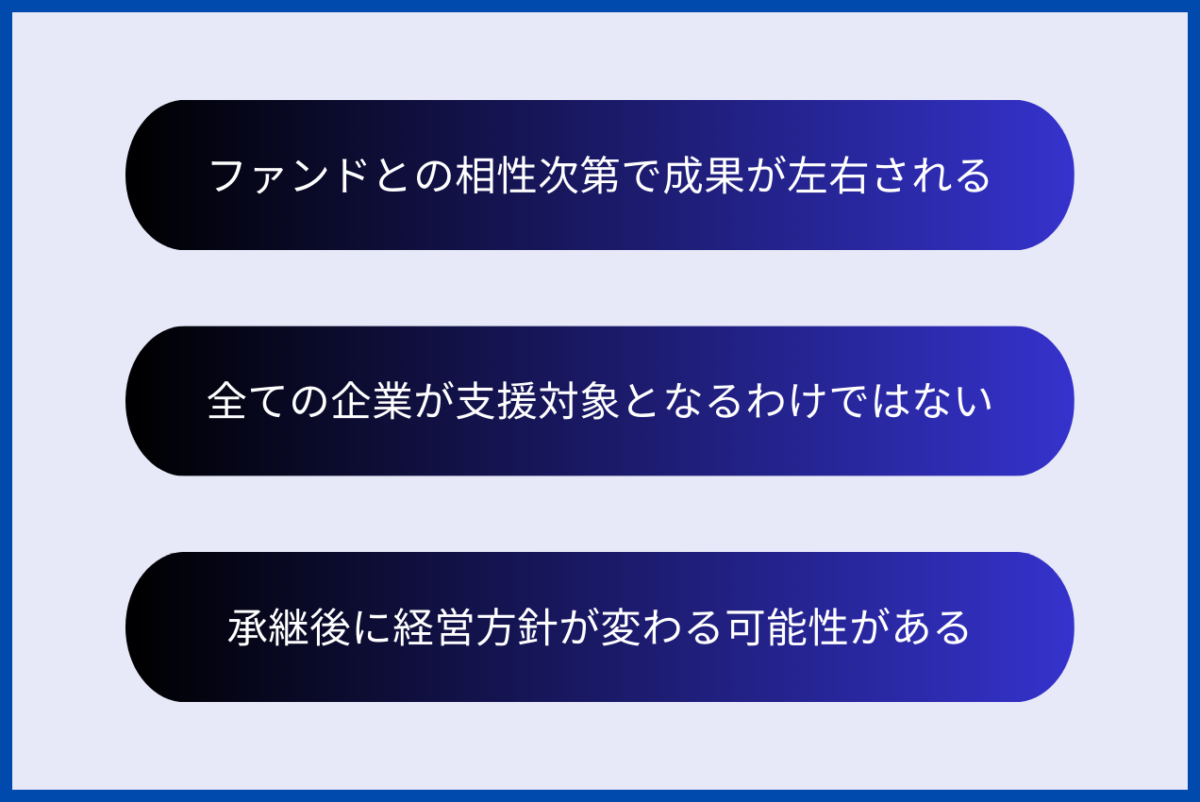
一方で、事業承継ファンドの活用には注意すべきリスクも存在します。ファンドの選定ミスや支援対象外とされる可能性、さらには承継後の経営方針変更といった懸念点も見過ごせません。
あらかじめデメリットを理解しておくことで、後悔のないファンド選びとスムーズな事業承継が可能になります。ここでは、事業承継ファンドを利用する際に想定される代表的なデメリットについて詳しく説明します。
事業承継ファンドの支援が効果を発揮するかどうかは、企業とファンドの相性に大きく左右されます。
ファンドにはそれぞれ得意とする業種や事業フェーズがあり、対象企業との間にミスマッチがあると、期待した成果が得られないリスクがあります。さらに、ファンドごとに経営支援のスタンスや投資方針も異なるため、事前に十分な情報収集と見極めが欠かせません。
相性の良し悪しは事業の将来に大きな影響を及ぼすため、慎重なファンド選定が必要です。
事業承継ファンドは、あくまで投資によって利益を得ることを目的としています。そのため、財務状況が著しく悪化していたり、将来的な成長見込みが乏しいと判断される企業は、支援の対象外とされることもあります。
そのため、支援を希望しても、ファンド側から断られるケースがあることは理解しておく必要があります。経営者としては、自社の財務体質を見直し、魅力ある企業に整えておくことが求められます。
事業承継ファンドは数年後の売却を見越して企業に投資するため、承継後にファンドが別の買い手に会社を売却することがあります。
会社が売却された場合、新たな経営者によって会社の方針や事業戦略が大きく変更される可能性も否定できません。結果として、創業者の意志や経営哲学が後世に引き継がれない懸念があります。
こうしたリスクを回避するためにも、ファンドとの契約時には将来の売却に関する条件や意向を明確にしておくことが重要です。
事業承継を円滑に進めるためには、自社に合った事業承継ファンドの選定が重要です。国内にはさまざまなファンドが存在しますが、それぞれが異なる特徴と支援体制を持っています。以下では代表的な4つの事業承継ファンドについて、それぞれの特性や支援内容を詳しく解説します。
中小機構の事業承継ファンドは、「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」が運営する公的性格の強いファンドです。
このファンドの大きな特徴は、利益追求を第一とせず、中小企業の健全な継続と成長を重視した支援方針を持っている点にあります。出資構造としては、中小機構がファンド組成額の50%を担い、残りを民間の金融機関が補う仕組みが採用されています。
経営支援の内容も幅広く、後継者育成、販路拡大、財務の安定化など多岐にわたる支援が可能です。支援が公的立場から行われるため、経営者としても安心して相談しやすい環境が整っているのが魅力です。
日本投資ファンドは、事業承継分野で実績豊富な日本M&Aセンターと、日本政策投資銀行が共同で設立したファンドです。両者が出資比率50%ずつを持っているため、民間の専門性と政府系金融機関の信用力が融合した支援体制を提供することが可能になっています。
最大の強みは、日本M&Aセンターが培ってきた豊富な事業承継ノウハウと全国に張り巡らされたネットワークを活かした柔軟な支援です。支援対象企業の審査基準も比較的寛容であり、成長意欲のある中堅・中小企業であれば、広く門戸が開かれています。
SBI地域事業承継ファンドは、SBIホールディングスの子会社によって2019年に設立された比較的新しいファンドです。地方創生の一環として、日本各地で後継者不在に悩む中小企業を支援することを目的としています。
SBI地域事業承継ファンドの大きな特徴は、「小規模な企業にも積極的に投資する」という方針です。従来のファンドでは支援対象となりにくかった規模の企業にも目を向けており、地域密着型の経営支援を行うことで、企業の存続だけでなく地域経済の活性化も同時に図っています。今後の展開が非常に注目されるファンドの一つといえるでしょう。
プライベートエクイティファンド、通称PEファンドは、機関投資家や個人投資家から資金を集め、未上場企業の株式を取得して経営に関与し、企業価値を高めた上で売却益を得ることを目的としています。そのなかでも事業承継ファンドとして機能するPEファンドの代表例が「日本プライベートエクイティ株式会社」です。
同社は、従業員の自立を促し、オーナー依存型の経営から組織経営への転換を得意としています。創業経営者の引退とともに、企業の成長支援とオーナー交代を成功させた実績があり、ファンドとしての信頼性の高さがうかがえます。組織としての独立性を高めたい企業にとっては、特に効果的な選択肢となるでしょう。
PEファンドについては以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。
→PE(プライベートエクイティ)ファンドとは?仕組みや流れ、メリットやデメリットを詳しく解説
事業承継ファンドを活用すれば、後継者不在の企業でも第三者へのスムーズなバトンタッチが可能となります。ファンドによる支援は資金面だけでなく、経営の安定化や成長支援にもつながるため、多くの中小企業にとって現実的な選択肢となっています。プロセスはある程度共通しており、以下のような流れで進められます。
1.ファンド運営会社が投資家から出資を募り、事業承継ファンドを組成する
2.経営者が専門家を介すか、あるいは直接ファンドに相談を持ちかける
3.秘密保持契約を締結し、財務情報や経営実態などを開示する
4.条件に問題がなければ、基本合意書を取り交わす
5.譲渡価格や支援内容などの条件調整を行う
6.弁護士・会計士などによるデューデリジェンス(買収監査)を実施する
7.最終的な譲渡契約を締結する
8.クロージングとして、株式譲渡と対価の受け渡しを実行する
9.ファンドによる経営支援がスタートする
10.数年後、企業価値が高まった段階でファンドが株式を売却し、投資を回収する
なお、各ステップの進め方や期間はファンドごとに多少異なるため、具体的な進行は事前に担当者と十分に確認しておくことが重要です。
デューデリジェンス、クロージングについては以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。
→DD(デューデリジェンス)とは?目的・M&Aの際の流れ・費用を解説
→M&Aにおけるクロージングとは?手続きや流れ、必要書類を解説
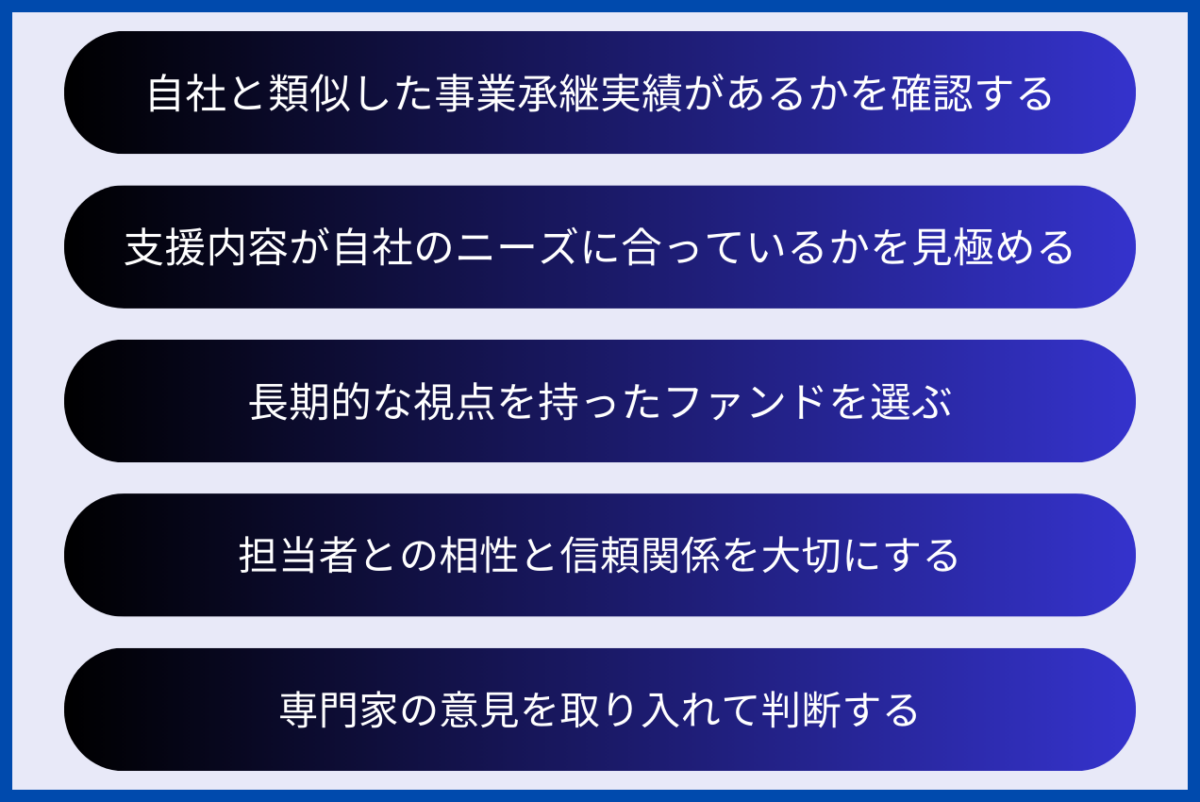
事業承継ファンドを活用することで、後継者不在や経営課題を解決できる可能性が広がりますが、すべてのファンドが自社に適しているとは限りません。ファンドごとに得意分野や支援内容、投資スタンスは異なっており、選定を誤れば期待した効果が得られないリスクもあります。
特に注意したいのが、「どんな支援をしてくれるのか」「どのくらいの期間・方法で株式を売却するのか」といった点です。経営支援や成長サポートに力を入れるファンドもあれば、短期的な利益を重視するファンドもあります。また、投資後5年を目安に株式を売却するのが一般的ですが、その柔軟性もファンドによって異なります。これらは売却側にとって非常に重要な判断材料です。
だからこそ、自社にとって最適なファンドを見極めるためには、いくつかの重要な判断軸を押さえておく必要があります。ここでは、事業承継ファンドを選ぶ際に特に重視すべきポイントを、わかりやすく整理して解説します。
事業承継ファンドを選ぶ際は、過去の支援実績に目を向けることが非常に重要です。ファンドごとに得意とする業種や企業規模が異なるため、自社と類似した事例に携わった経験があるファンドの方が、効果的な支援を提供してくれる可能性が高いです。
たとえば、自社と同業種・同規模の企業に対して成功裡に事業承継を行った実績がある場合、同じような課題やリスクを把握しているため、的確な提案や支援が期待できます。逆に、専門外のファンドでは、ノウハウや経験が不十分なことで、期待した効果が得られないおそれもあります。
そのため、事業承継ファンドを選定する際は、単に「実績があるかどうか」だけでなく、「自社とどれだけ類似した企業への支援経験があるか」という観点で確認することが重要です。
ファンドの支援内容が自社のニーズにマッチしているかどうかは、事業承継成功の可否を大きく左右します。事業承継ファンドといっても支援の内容や強みは多種多様で、承継に特化しているファンドもあれば、成長支援や再建支援に重点を置くファンドも存在するため、自社のニーズに合ったファンドを選ぶことが重要です。
仮に、事業承継そのものよりも、経営再建や収益改善に重点を置くファンドを選んでしまうと、自社が求める支援とは方向性がずれてしまい、期待した効果が得られない可能性があります。
相談時には、ファンド側に自社が求める支援内容を明確に伝え、それに対する具体的な対応策や支援体制を確認することが必要です。双方向の認識を共有できるファンドであれば、事業承継後も安心して連携が取れるでしょう。
ファンドによっては、短期的に企業価値を高めることを目的として、早期の利益確定を目指すケースもあります。しかし、自社が求めるのが持続的な成長や経営理念の承継である場合には、そうした短期志向のファンドは適していません。
短期的な利益追求を優先するファンドでは、場合によっては不動産売却やリストラなど、企業風土や従業員の士気に影響を与える手段が取られることもあります。その結果、社内の混乱や人材流出が起こるおそれもあるため、注意が必要です。
一方で、企業価値の向上を中長期的な目線で捉え、段階的な支援を重視するファンドであれば、経営理念や従業員の意識を保ちながら、企業の持続的な成長が見込めます。選定時には、ファンドの運営方針や投資スタンスをよく確認しておくことが肝要です。
事業承継ファンドを活用する際には、担当者との相性や信頼関係も極めて重要な判断材料です。ファンドとのやり取りは一過性のものではなく、事業承継の前後を通じて長期間にわたり密接な関係を築くことが必要です。
たとえば、経営者の価値観や想いを理解し、それを尊重した提案や対応をしてくれる担当者であれば、安心して経営のバトンを託すことができます。反対に、対応が形式的だったり、話の通じにくい担当者では、信頼関係を築くのが難しく、事業承継に支障をきたすリスクもあります。
そのため、最初の面談や打ち合わせの段階で、担当者の熱意・誠実さ・専門性を見極めることが求められます。少しでも不安を感じる場合は、無理に話を進めず、他のファンドや担当者も検討する柔軟な姿勢が大切です。
事業承継ファンドの選定には、専門的な知識が不可欠です。経営者自身がすべてを判断するのは難しいため、信頼できる専門家の意見を取り入れることが、失敗を回避するための有効な手段になります。
たとえば、M&A仲介会社、公認会計士、税理士といった第三者の専門家は、数多くの事業承継を支援してきた経験と知見を持っています。こうした専門家のアドバイスを活用することで、自社に最適なファンドを見極める視点を得られるでしょう。
また、事業承継ファンドのみにとどまらず、他の手段も含めた提案が受けられることもあるため、より幅広い選択肢の中から、自社にとって最適な事業承継の道を見つけることが可能になります。最終的な決定を下す前に、第三者の視点を取り入れることを強く推奨します。
事業承継における専門家については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。
→M&Aアドバイザーとは?仕事の内容・役割や依頼する際の注意点を紹介
→【徹底比較】M&A仲介会社・マッチングサイト一覧!大手5社はどこ?
→M&Aにおける弁護士の役割とは?業務内容や費用相場を徹底解説
事業承継ファンドは、後継者不在に悩む企業の存続と成長を支える有効な手段として注目されています。ここでは、全国各地で実際に行われた事業承継ファンドの活用事例を紹介し、企業がどのようにファンドを活用して事業承継と成長支援を実現しているかを具体的に紹介します。
栃木県小山市に本社を構える信庄産業株式会社は、鋼管の製造を手掛ける老舗企業であり、農業設備や建築資材の分野で長年の実績を積み上げてきました。しかし、変化の激しい経営環境に対応するためには、将来を見据えた経営体制の刷新が不可欠となり、事業承継ファンドの活用を決断します。
ロングブラックパートナーズのグループ会社LBPIが運営する「継承ジャパン投資事業有限責任組合」は、信庄産業の株式を取得し、事業承継と同時に成長支援にも着手しました。今後は、地域金融機関との連携のもとで増資を行い、設備投資と経営基盤の強化を進めていく方針です。
三重県四日市市の須藤株式会社は、鋼材や配管資材、建設資材などの卸売業を展開する企業です。事業承継に課題を抱えていた同社に対し、三十三フィナンシャルグループと名南経営キャピタルが連携して設立した「三十三事業承継1号投資事業有限責任組合」が支援に乗り出しました。
このファンドは、地域の中小企業を対象に、経営のバトンを次世代につなぐことを目的としています。須藤株式会社の株式を取得することで、スムーズな承継と今後の成長支援に向けた体制が整備されました。
岐阜県の和洋菓子工房「泉屋」は、自社の伝統的な味を後世に残したいという思いから、事業承継に取り組みました。同社の経営者は、「想いを引き継いでくれる人物」であることを最も重視し、事業支援・引継ぎセンターを通じて後継者探しを開始。
やがて、和菓子の企画販売経験はあるものの製造経験がない候補者が現れましたが、丁寧な研修を経て課題を克服し、事業承継が実現しました。前オーナーは承継後も執行役員として企業に関わり、円滑な引き継ぎをサポートしています。
徳島県にある老舗酒蔵・三芳菊酒造は、1903年創業の歴史ある企業ながら、経営者の高齢化と需要の変化により存続が危ぶまれていました。そこで、SBIホールディングスの子会社であるSBI地域事業承継投資が運営するファンドが支援を実施。
投資によって経営再建への道が開かれ、販売強化や海外展開、観光事業など多角的な経営戦略を展開する体制が整いました。また、外部のプロフェッショナルを取締役に迎え、企業価値の向上と地域の活性化を目指す新たな取り組みが始まっています。
空中店舗の開発という独自のビジネスモデルで注目を集める株式会社フィル・カンパニーは、創業間もない2007年に西武信金キャピタルが運営するファンドから2億円の出資を受けました。
駐車場の上空スペースを活用するという新しい発想を事業化するには、安定した資金が必要不可欠であり、ファンドの出資が事業基盤の構築を支えました。その後も継続的に資金調達を行い、2017年時点で完成した空中店舗は83件にのぼり、成長企業としての地位を確立しています。
チェーンソー用のガイドバーなどを製造するダイアトップ株式会社は、2017年に日本プライベートエクイティ(JPE)からの出資を受けて資本提携を実施しました。
同社は、JPEの経営支援を受けながら、組織改善や成長戦略の構築に注力。その成果をもとに、2022年11月には百五みらい投資が運営するAIDMA2号投資事業有限責任組合に株式が売却され、次のフェーズへと事業が引き継がれました。JPEの支援によって、企業としての成長力を高めながら、持続可能な承継を実現した代表的な事例です。 会社売却や事業承継など、M&Aに関するお悩みは、ぜひM&A Leadへご相談ください。 当社は「完全成功報酬制」を採用しており、譲渡が成立し譲渡対価が入金されるまでは一切料金をいただきません。お気軽にご相談いただけます。 また、知識・支援実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、ご相談からクロージングまで、売主様に徹底的に寄り添いサポートいたします。 さらに、当社のアドバイザーだけでなく、当社が運営するM&Aアドバイザー紹介プラットフォームにご登録いただいているM&Aアドバイザー様のネットワークも活用可能なので、どのような業界・業種の案件にもご対応可能です。 当社はこの強みをフルに活用して、M&Aをお考えのオーナー様に徹底的に寄り添い、売却成功までサポートいたします。 無料相談は随時お受けしておりますので、お電話・Webよりお気軽にお問い合わせください。
事業承継ファンドは、後継者不足に悩む中小企業にとって、単なる承継手段ではなく、企業の未来を切り拓くための大きな選択肢です。
本記事では、その仕組みや活用の流れ、実際の支援事例を解説してきました。今後、事業承継を検討する際には、自社に合ったファンドの選定と、信頼できるパートナーとの連携を検討していくにあたり、本記事が参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
M&A・事業承継のご相談はお任せください。 経験豊富なM&Aアドバイザーが、無料でお話をお伺いし、M&Aに捉われず、ご相談いただきました会社・事業オーナー様に最適なご提案させていただきます。 まずはお気軽にお問い合わせください。
POPULAR