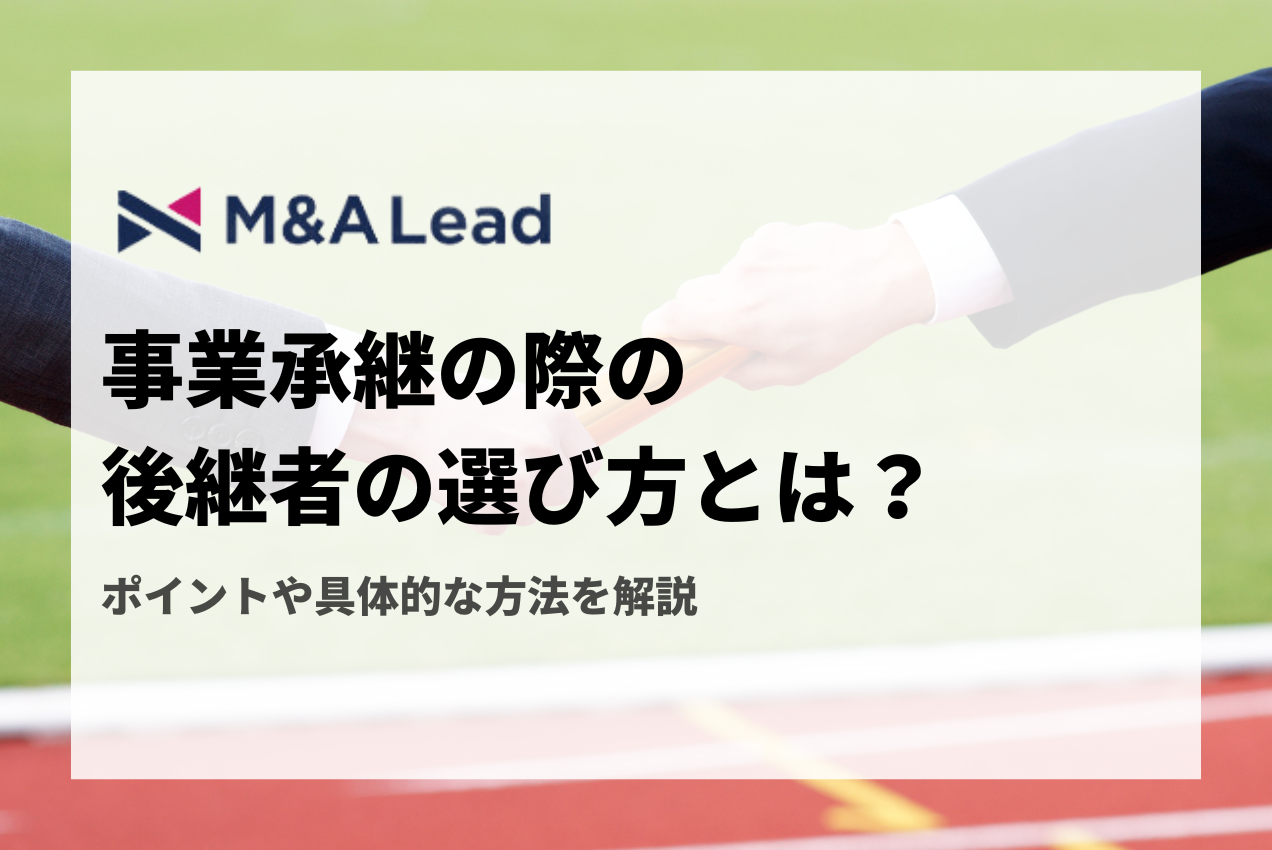
事業承継は、企業の未来を左右する極めて重要な経営課題です。特に中小企業では、後継者不在が深刻な問題となり、多くの企業が廃業の危機に直面しています。
本記事では、「後継者とは何か」「何を引き継ぐべきか」といった基本知識だけでなく、後継者不足の背景や現状についてもわかりやすく解説していきます。
この記事の監修者目次
企業の経営を次世代へと受け継ぐ「事業承継」は、経営者にとって避けては通れない大きな課題です。特に近年では、経営者の高齢化が進む一方で、後継者が決まらないまま時間だけが過ぎてしまうケースが増えており、企業の存続に深刻な影響を及ぼしています。
事業承継を成功させるには、まず「後継者とは何か」「どのような資源を承継するのか」といった基本的なポイントを正しく理解することが欠かせません。さらに、なぜ中小企業において後継者不足が深刻化しているのかという現状も把握しておく必要があります。
ここでは、事業承継や後継者に関する基礎的な知識を解説していきます。
事業承継における後継者とは、現経営者の引退後に会社の経営を担う人物のことを指します。ただし、単に役職や株式を引き継ぐだけでなく、経営者の理念や経営に対する想い、従業員との信頼関係など「目に見えない資産」も含めて受け継ぐことが求められます。
したがって、真の意味での後継者とは、単に形式的に会社を継ぐ存在ではなく、企業文化や経営者の精神までを引き継ぎ、それを活かして会社の未来を築ける人物を意味します。
特に中小企業においては、オーナー経営者が長年の経験や人脈で築き上げてきた価値を引き継ぐ必要があるため、後継者の選定は慎重に行わなければなりません。後継者となる人物には、実行力や判断力だけでなく、社内外からの信頼、そして会社を導いていくリーダーシップが不可欠です。
そのため、早い段階から後継者の候補を見極め、育成に取り組むことが、円滑な事業承継を実現するための鍵となります。
事業承継という言葉からは、代表者の交代や株式の譲渡といった制度的な手続きが想起されがちですが、実際に引き継ぐべきものは多岐にわたります。具体的には、「経営権」「資産」「知的資産」の3つが柱となります。
まず、経営権は会社を意思決定するための根幹であり、株式の過半数を保有することで実質的な経営のコントロールが可能になります。次に、資産には工場や事務所といった不動産、設備、運転資金、金融機関からの借入金などが含まれます。そして最後は見落とされがちである知的資産です。知的資産とは、経営者が長年にわたって築き上げたノウハウ、従業員のスキルや取引先との信頼関係、企業理念など、目には見えないが会社の競争力の源泉となるものです。
上記3点を後継者がきちんと引き継ぐことができるかどうかで、事業承継の成否は大きく左右されます。そのため、表面的な手続きだけでなく、経営資源の本質を整理し、丁寧に承継を進めることが重要です。
現在、日本では中小企業の事業承継が深刻な局面を迎えています。最大の要因は「後継者の不在」です。帝国データバンクや中小企業庁の調査によれば、いわゆる2025年問題と言われる、経営者の高齢化が進む一方で、約7割もの中小企業が後継者を見つけられていないという実態があります。
後継者不足の背景には、さまざまな理由が存在します。たとえば、経営者自身が引退のタイミングを見定められず後継者選定が遅れるケースや、子どもに継がせることを望まない、あるいは子ども自身が継ぐ意思を持っていないといった家庭の事情も少なくありません。また、将来性に不安を感じたり、経営者の負担の大きさに尻込みしてしまう人材が多いことも影響しています。
結果として、企業としては成長の余地があっても、後継者が見つからないために廃業や解散を選ばざるを得ない企業が年々増加しています。特に団塊の世代の引退が進んでいる今、事業承継の問題は社会全体にとって喫緊の課題となっています。中小企業の存続と地域経済の活力を維持するためにも、後継者の育成や承継手段の多様化に早急に取り組むことが必要です。 会社売却や事業承継など、M&Aに関するお悩みは、ぜひM&A Leadへご相談ください。 当社は「完全成功報酬制」を採用しており、譲渡が成立し譲渡対価が入金されるまでは一切料金をいただきません。お気軽にご相談いただけます。 また、知識・支援実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、ご相談からクロージングまで、売主様に徹底的に寄り添いサポートいたします。 さらに、当社のアドバイザーだけでなく、当社が運営するM&Aアドバイザー紹介プラットフォームにご登録いただいているM&Aアドバイザー様のネットワークも活用可能なので、どのような業界・業種の案件にもご対応可能です。 当社はこの強みをフルに活用して、M&Aをお考えのオーナー様に徹底的に寄り添い、売却成功までサポートいたします。 無料相談は随時お受けしておりますので、お電話・Webよりお気軽にお問い合わせください。
現在、日本全国の中小企業が直面している最大級の経営課題のひとつが「後継者不足」です。事業承継に支障をきたしている企業が増加しており、将来の経済構造に大きな影響を及ぼす恐れも指摘されています。とくに高齢化が進む中小企業の経営者層では、後継者が不在のまま引退時期を迎えるケースが後を絶ちません。
日本政策金融公庫総合研究所の調査(2023年)によると、全国の中小企業のうち、すでに後継者が決まっている企業はわずか10.5%にとどまっています。一方で、廃業の意向を示している企業は全体の57.4%にものぼり、過半数の企業が後継ぎ不在を理由に経営の継続を断念しようとしている状況が浮き彫りになっています。
企業の規模別にみても、従業員1~4人の企業では後継者決定率がわずか5.6%。比較的人員規模の大きい企業でも、後継者が決まっている割合は20%台にとどまっており、規模に関係なく後継者難が蔓延しています。
また、東京商工リサーチの2023年調査によると、経営者の平均年齢は63.8歳にまで上昇しており、80代以上の経営者のうち約32%が後継者未定という結果も報告されている状況です。さらに、休廃業・解散件数は2009年の25,000件弱から、2023年には49,788件へと倍増しています。高齢化と後継者不在のダブルパンチにより、企業の終焉が現実のものとなっています。
後継者不足がここまで深刻化している背景には、複数の要因が絡み合っています。代表的な4つの原因を詳しく解説します。
これまで日本では、親から子へと事業を受け継ぐ「親族内承継」が主流でした。しかし、少子化の影響により、そもそも後を継がせるべき子どもがいないというケースが増えています。加えて、時代の価値観の変化により、親が子に継がせることを強制しなくなった結果、親族内での承継は年々減少の一途をたどっています。
親族が後を継がない場合、従業員や役員にバトンを渡す「社内承継」が次の選択肢になります。しかしながら、個人事業や小規模企業では、そもそも従業員がいない、あるいは適任者がいないことも多く、社内承継もままなりません。仮に後継候補がいても、株式の買い取り資金が工面できず、実現に至らないケースもあります。
従業員への事業承継については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。
→従業員承継とは?メリット・デメリットや承継の流れを解説
事業の将来性に疑問を感じている場合、親族も社内の人材も後継者として名乗り出る可能性は低くなります。業績が伸び悩んでいたり、業界全体が衰退傾向にあったりすれば、将来に希望が持てず、後継者不足に拍車がかかります。経営者自身が「自分の代でやめる」と決め込んでいるケースもあり、後継者不在率をさらに押し上げる要因のひとつとなっています。
「後継者がいない」と嘆く経営者の中には、実際には探す方法を知らないだけ、というケースもあります。後継者探しには時間も労力も必要で、専門的な支援を受けなければ進めるのが難しいこともあります。しかし、情報収集不足や相談先の不明瞭さが原因で、対策が後手に回ってしまう経営者が多いのが現実です。
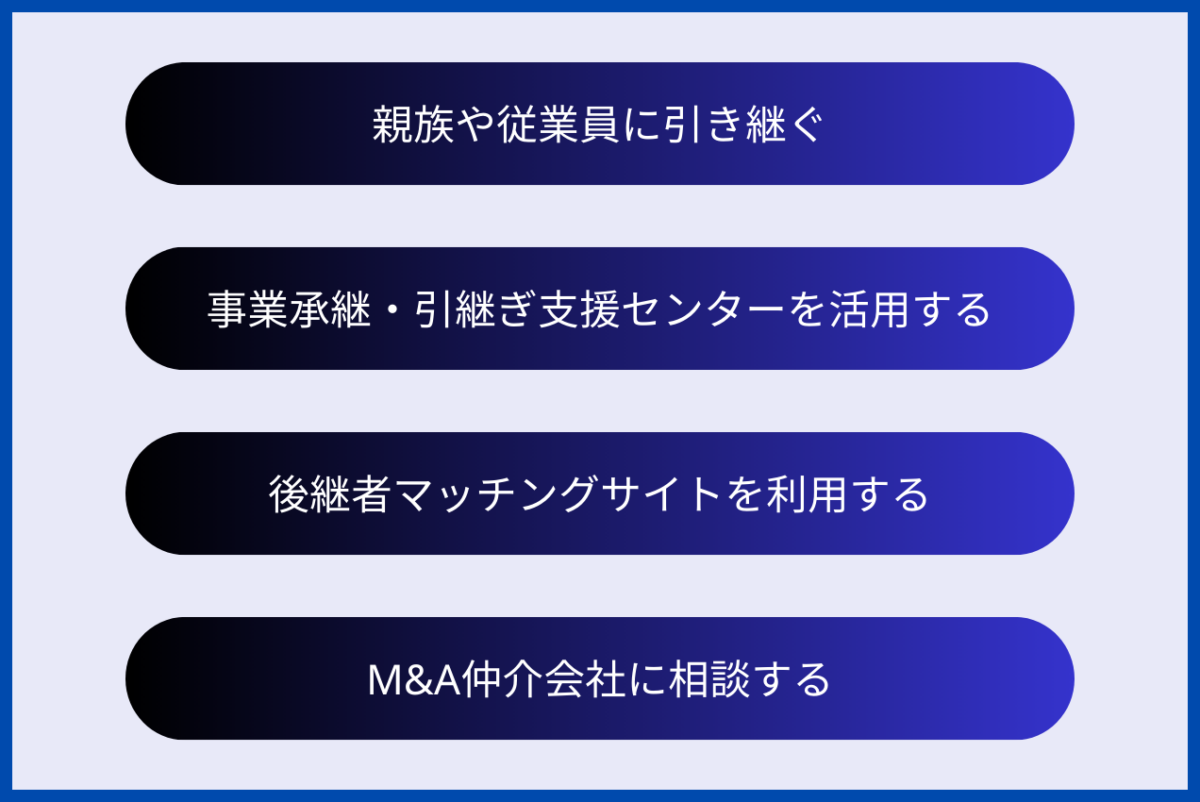
事業承継において最も難しい課題のひとつが「誰に引き継ぐのか」、つまり後継者選びです。近年は、親族や従業員からの選定だけでなく、外部の人材を活用する選択肢も広がっています。ここでは、後継者を探すために有効な4つの方法を紹介し、それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく解説します。
もっとも一般的で多くの企業で採用されているのが、親族や従業員に事業を引き継ぐ方法です。とくに親や祖父母が経営する企業を子や孫が継ぐ「親族内承継」は、従業員や取引先からの理解を得やすく、円滑な承継が期待できます。また、既に企業内にいる従業員であれば、業務への理解が深く、信頼関係も構築されている点が強みです。
この方法の最大のメリットは、承継後の混乱を最小限に抑えられることです。早期に後継者を決めておけば、長期的な育成期間を確保でき、経営理念や現場感覚を時間をかけて伝承することが可能になります。
一方で、指名された親族や従業員が事業承継に前向きでなかった場合、後継者不在の状態に逆戻りしてしまうリスクがあります。そのため、候補者の意思確認は早期に行い、互いに納得したうえで準備を進める必要があります。
親族や従業員に適任者がいない場合には、国が支援する「事業承継・引継ぎ支援センター」の利用を検討するのも有力な選択肢です。全国の都道府県に設置されている事業承継・引継ぎ支援センターは、中小企業庁の委託事業として運営されており、事業承継に関する幅広い相談を受け付けています。
なかでも注目されているのが「後継者人材バンク」です。この制度では、起業意欲のある人材と、後継者を必要とする中小企業をマッチングしており、公的なサービスであるため相談や登録は無料です。
ただし、マッチングされた候補者が必ずしも適任とは限らない点には注意が必要です。もし相性や資質に問題があれば、再度最初から後継者探しを行う必要があります。また、マッチング後の契約手続きや法務対応は、紹介された士業事務所に依頼する必要があり、その際には費用が発生します。
インターネットを活用した後継者探しの方法として、後継者求人のマッチングサイトを利用するという選択肢もあります。後継者マッチングサイトは、後継者を探している企業と、後継者になりたい個人を結びつけるプラットフォームで、全国から希望者を募ることができます。
後継者マッチングサイトの魅力は、地理的な制約がなく、全国規模で後継者候補を探せる点です。条件設定によって、自社の経営方針や業種にマッチする人物を効率的に見つけられる可能性があります。
一方で、すべてのマッチングサイトが同じ品質というわけではありません。中にはユーザー数が少なく、後継者候補と出会うまでに時間がかかるケースもあります。また、登録料や成約時の費用がかかるサイトもあるため、利用前には運営企業の信頼性や費用体系を必ず確認する必要があります。
親族や従業員、または人材マッチングで適任者が見つからない場合には、M&A仲介会社を通じて事業を譲渡することで後継者問題を解決する方法もあります。M&Aは、買い手となる企業や個人が新たな経営者として会社を引き継ぐ形で事業承継が成立します。
この方法のメリットは、後継者候補の幅が圧倒的に広がることにあります。さらに、M&A仲介会社のアドバイザーがマッチングから契約、手続きまでを一貫してサポートしてくれるため、初めてのM&Aでも安心して進めることができます。
ただし、M&A仲介会社によって報酬体系やサービス内容は異なるため、相談する会社選びは非常に重要です。成約までにかかる費用や中間金の有無、サポート体制などを確認し、自社の状況に適したパートナーを選びましょう。
M&A仲介会社については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。
→【徹底比較】M&A仲介会社・マッチングサイト一覧!大手5社はどこ?
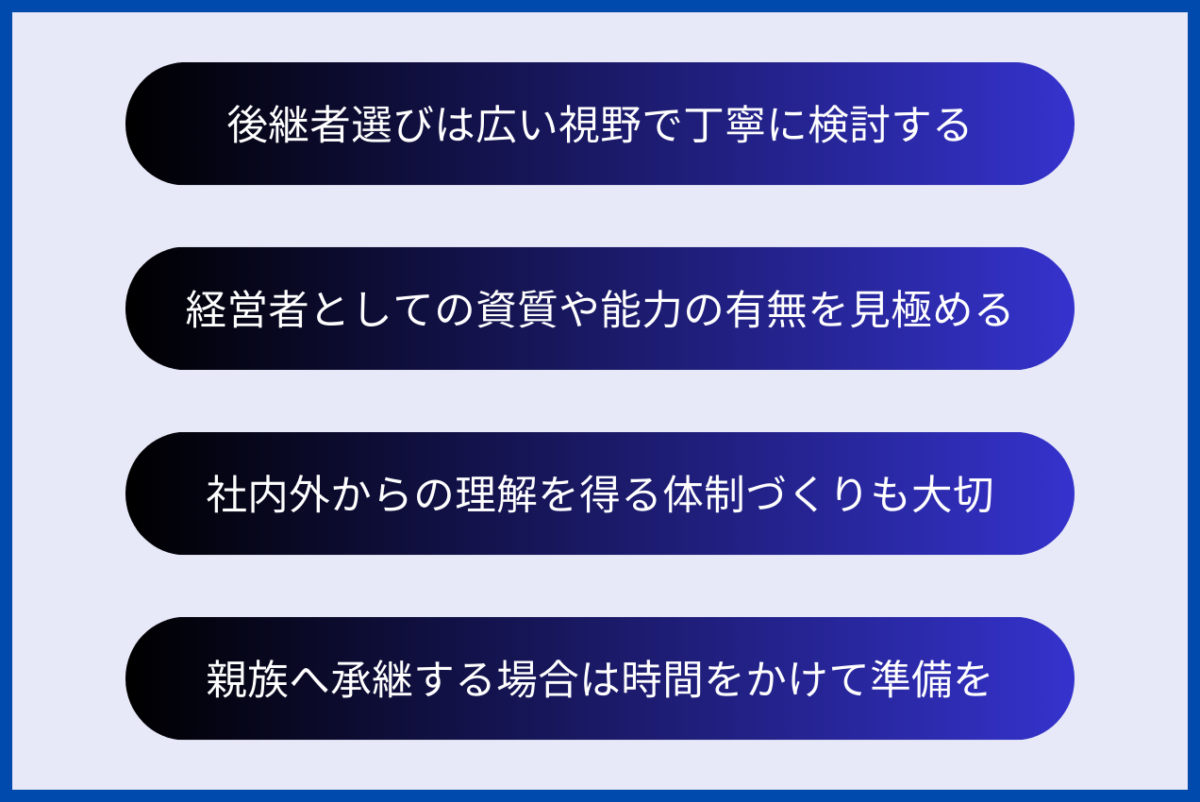
事業承継を成功に導くためには、後継者の選定が最も重要なステップです。どれだけ周到に承継計画を立てても、後継者に経営者としての資質が備わっていなければ、企業の存続や成長は危うくなります。そこで今回は、後継者選びで押さえておくべきポイントについて、実務的な視点から詳しく解説します。
まず意識すべきは、後継者の選定にあたっては「親族だから」「長年働いているから」といった表面的な理由だけで決めてはいけないという点です。事業承継の準備が整い、いよいよ次世代にバトンを渡す段階では、たとえ候補者が明確でない場合であっても、幅広い視点から適任者を探すことが求められます。
親族や従業員への承継を考える場合でも、感情的なつながりだけで判断するのではなく、本人の意思や能力、将来のビジョンについてしっかりと対話を重ねる必要があります。経営を引き継ぐ以上、株式や経営資源の移転だけでなく、社内外の信頼関係や事業理念の継承も重要なポイントとなるため、周囲の理解や納得を得ることも欠かせません。
どうしても一対一で話し合うのが難しい状況であれば、信頼できる第三者や専門家を交えてプロセスを進めるのも良い選択です。また、後継者候補が社内に見当たらない場合には、M&A仲介会社や後継者マッチングサービスの活用も視野に入れて、柔軟なアプローチで選定作業を進めることが重要です。
事業承継の専門家については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。
→M&Aアドバイザーとは?仕事の内容・役割や依頼する際の注意点を紹介
→M&Aにおける弁護士の役割とは?業務内容や費用相場を徹底解説
後継者に求められる最も基本的な条件は、経営者としての総合的な能力を備えているかどうかです。とりわけ財務・会計に関する基礎知識や業界への理解、そして事業戦略を描ける思考力などは不可欠な要素となります。
企業の規模によって求められる資質も異なります。たとえば、小規模企業では経営者が現場にも深く関与するため、実務能力や現場感覚が重視されます。一方で、中規模以上の企業では、従業員や幹部を統率するリーダーシップ、意思決定力、そして組織全体をマネジメントする力がより必要です。
後継者選びを成功させるためには、単に能力のある人物を選ぶだけでは不十分です。承継後のスムーズな運営のためには、社内外の関係者からの信頼と協力を得る体制を整えることが重要です。
特に中小企業では、従業員との関係性や取引先との信頼関係が経営基盤を支えているため、新たな経営者に対して理解と協力が得られなければ、組織の結束が弱まり経営が不安定になる恐れもあります。そのため、後継者が社内で一定の実績を積むことや、時間をかけて関係者との信頼構築を図るプロセスが必要です。
企業規模が大きくなるほど、後継者単独で全てを担うのは難しくなります。したがって、後継者を支える経営幹部の育成や、承継後の新体制づくりに向けた準備も同時に進めるべきです。経営体制が整っていれば、取引先や金融機関からの信頼も得やすく、承継後の経営が安定しやすくなります。
親族への事業承継を考える場合には、時間をかけた丁寧なプロセスが不可欠です。たとえ子どもや親族であっても、いきなり経営を任せられるほど準備ができているとは限りません。経営の実務はもちろん、業界特有の商慣習や人間関係の構築にも時間が必要です。
そのため、できるだけ早い段階で親族を入社させ、少しずつ業務に関わらせることが望ましいです。重要な会議や取引先とのやり取りに同席させるなどして、自然なかたちで経営の現場を学ばせることが、将来的な信頼と自信につながります。
親族承継は心理的なハードルが低い反面、準備不足で承継を急いでしまうと失敗につながりやすい側面があります。後継者自身が経営に前向きな姿勢を持てるよう、事前の教育や意識醸成を丁寧に行うことが、承継成功への鍵となるのです。
事業承継の際の親子トラブルについては以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。
→事業承継における親子トラブルとは?承継成功のポイントも解説
事業承継を円滑に進めるためには、経営者個人の努力だけでなく、企業としての組織的な準備も重要です。多くの中小企業では、経営者の高齢化が進んでいるにもかかわらず、事業承継に向けた具体的な準備が整っていないケースが少なくありません。十分な準備がなければ、後継者が円滑に経営を引き継げず、事業そのものの継続が危ぶまれる可能性もあります。そのため、会社と経営者の両方の視点から、早期かつ計画的な準備に取り組むことが不可欠です。
まずは、会社が行うべき主な準備について解説していきます。
企業として最初に取り組むべき準備は、財務状況や資産状況の明確化です。特に注意すべき点は、簿外債務や不明瞭な資産の存在です。事業承継のタイミングでこうした要素が発覚すると、会社の評価が大幅に下がり、後継者の意欲を削ぐ可能性も否定できません。第三者承継を行う場合には、デューデリジェンスで隠れた負債が明らかになることもあり、信頼を損なう事態にもつながります。
このようなリスクを回避するには、日常的に帳簿を整理し、債務や財産、株主構成などを明確にしておくことが肝要です。加えて、事業承継の方向性や計画を社内全体で共有しておくことで、従業員の協力体制も整いやすくなります。事業承継は一部の経営陣だけの課題ではなく、組織全体に関わる重大なテーマであるという意識づけが求められます。
デューデリジェンスについては以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。
→DD(デューデリジェンス)とは?目的・M&Aの際の流れ・費用を解説
事業承継を成功に導くためには、自社の持つ強みや成長可能性を再確認し、適切に伝える準備も必要です。近年、後継者が見つからない理由のひとつに「会社に魅力がない」という認識があるとされていますが、必ずしも実際に企業の価値が低いということではなく、強みがうまく言語化・整理されていないことに起因している場合もあります。
そこで、まずは自社の価値を客観的に見直すことが大切です。収益構造、取引先との関係性、知的資産などを把握し、後継者候補や外部投資家に対して自信を持って説明できる状態に整えておくことで、事業承継の話も前向きに進みやすくなります。
続いて、経営者が行うべき主な準備について解説していきます。
経営者個人として、まず取り組むべきは引退時期の決定です。多くの経営者は日々の業務に追われ、引退のタイミングを先延ばしにしがちですが、明確な時期を定めておかなければ、後継者の選定や育成のスケジュールも組みにくくなります。特に中小企業の場合、経営者の個人的な判断が企業全体の方向性に大きな影響を与えるため、早期の意思決定が重要です。
一般的には、60代前後をひとつの目安として引退時期を想定するのが望ましいとされています。そのうえで、後継者育成に必要な期間を逆算し、少なくとも5年から10年ほどの余裕を持って準備に取り組むことで、スムーズな承継が可能になります。
次に重要となるのが、どのような人物に事業を託すかという後継者像の明確化です。単に経営経験がある人物を探すのではなく、自社の経営理念や将来的な目標に沿った判断が求められます。そのためには、承継後に目指すべき経営戦略や収益目標などを具体的に設定し、それを達成できる人物像を定義する必要があります。
後継者候補が親族、従業員、あるいは外部人材のいずれであるかにかかわらず、「どのような資質を持った人に経営を任せたいのか」を明確にしておくことが、後継者選定の指針となります。また、この段階で専門家の支援を受けることで、経営の見通しや後継者育成の計画も立てやすくなるでしょう。
会社売却や事業承継など、M&Aに関するお悩みは、ぜひM&A Leadへご相談ください。
当社は「完全成功報酬制」を採用しており、譲渡が成立し譲渡対価が入金されるまでは一切料金をいただきません。お気軽にご相談いただけます。
また、知識・支援実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、ご相談からクロージングまで、売主様に徹底的に寄り添いサポートいたします。
さらに、当社のアドバイザーだけでなく、当社が運営するM&Aアドバイザー紹介プラットフォームにご登録いただいているM&Aアドバイザー様のネットワークも活用可能なので、どのような業界・業種の案件にもご対応可能です。
当社はこの強みをフルに活用して、M&Aをお考えのオーナー様に徹底的に寄り添い、売却成功までサポートいたします。
無料相談は随時お受けしておりますので、お電話・Webよりお気軽にお問い合わせください。
本記事では、事業承継に関する基礎知識から後継者不足の現状、さらには後継者の選定や準備に関する実務的な視点まで、幅広く解説してきました。事業承継は一朝一夕に進められるものではなく、計画的な準備と冷静な判断が求められます。自社の未来を託すにふさわしい後継者を見極めることはもちろん、企業の価値や理念をどのように継承していくかという視点も欠かせません。
本記事が、事業の継続を真剣に考える経営者の方の参考となれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
M&A・事業承継のご相談はお任せください。 経験豊富なM&Aアドバイザーが、無料でお話をお伺いし、M&Aに捉われず、ご相談いただきました会社・事業オーナー様に最適なご提案させていただきます。 まずはお気軽にお問い合わせください。
POPULAR