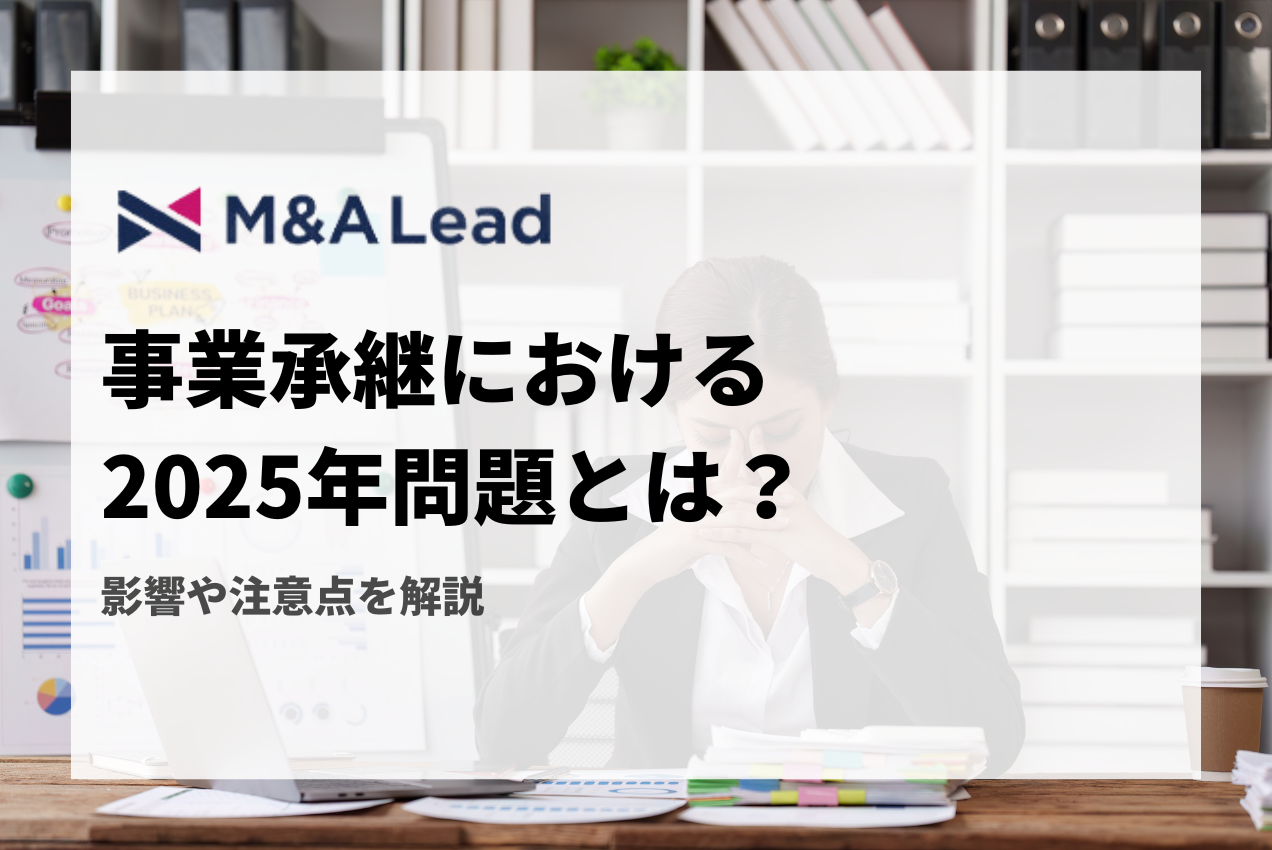
2025年には、日本の団塊の世代が75歳以上となり、高齢化が急速に進行します。高齢化に伴い、経営者の引退時期が重なることで、中小企業の事業承継問題が深刻化すると予測されています。
日本政府も事業承継支援策を打ち出してはいるものの、後継者探しの難航やM&Aの相手先不足といった課題が依然として解決されていません。多くの企業が対策を先送りにした結果、適切な事業承継の機会を逃し、廃業を余儀なくされるケースが増える可能性があります。
このような状況を回避するためには、企業は今から積極的に事業承継の準備を進める必要があります。本記事では、具体的な対策について解説します。
M&Aの基本的な概要については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。
→M&Aとは?概要・流れ・メリット・デメリット・成功ポイントを解説
目次
2025年問題とは、日本が直面する超高齢社会の進行に伴い、多岐にわたる影響が生じる社会的課題を指します。特に、戦後のベビーブーム(1947年〜1949年)に生まれた「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者となることで、医療・介護・年金といった社会保障分野に負担が増加すると考えられています。
しかし、問題は社会保障だけにとどまりません。中小企業や小規模事業者の事業承継にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。中小企業庁の調査によると、2025年までに70歳を超える経営者は約245万人に達するとされ、そのうち約127万社が後継者不在のまま廃業の危機に直面する可能性があると見込まれています。
もし企業が事業承継を果たせず廃業に至った場合、日本のGDPは約22兆円の損失を受け、650万人もの雇用が失われると推計されています。2025年問題は経済全体に大きな打撃を与える可能性があり、早急な対応が求められています。
2025年問題とよく比較されるのが2040年問題ですが、どちらも高齢化がもたらす課題を指しているものの、発生する状況や影響は異なります。
2025年問題は、団塊世代が75歳を超えることによって後期高齢者人口が急増し、医療や介護費用が膨らみ、事業承継が進まないことで企業の廃業が増加し、労働力人口の減少が加速することが主な課題です。
一方で、2040年問題は、団塊ジュニア世代が65歳に達し、高齢者人口が全体の35%に達することで、現役世代の減少がさらに深刻化し、社会保障負担の増大や公共インフラの老朽化による維持管理の負担増といった課題が発生することが予想されています。
2025年問題への適切な対応が2040年問題の影響を軽減するための鍵となるため、今のうちからしっかりと対策を進めることが重要です。 会社売却や事業承継など、M&Aに関するお悩みは、ぜひM&A Leadへご相談ください。 当社は「完全成功報酬制」を採用しており、譲渡が成立し譲渡対価が入金されるまでは一切料金をいただきません。お気軽にご相談いただけます。 また、知識・支援実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、ご相談からクロージングまで、売主様に徹底的に寄り添いサポートいたします。 さらに、当社のアドバイザーだけでなく、当社が運営するM&Aアドバイザー紹介プラットフォームにご登録いただいているM&Aアドバイザー様のネットワークも活用可能なので、どのような業界・業種の案件にもご対応可能です。 当社はこの強みをフルに活用して、M&Aをお考えのオーナー様に徹底的に寄り添い、売却成功までサポートいたします。 無料相談は随時お受けしておりますので、お電話・Webよりお気軽にお問い合わせください。
2025年問題が、事業承継にどのような影響を与えるのか解説していきます。
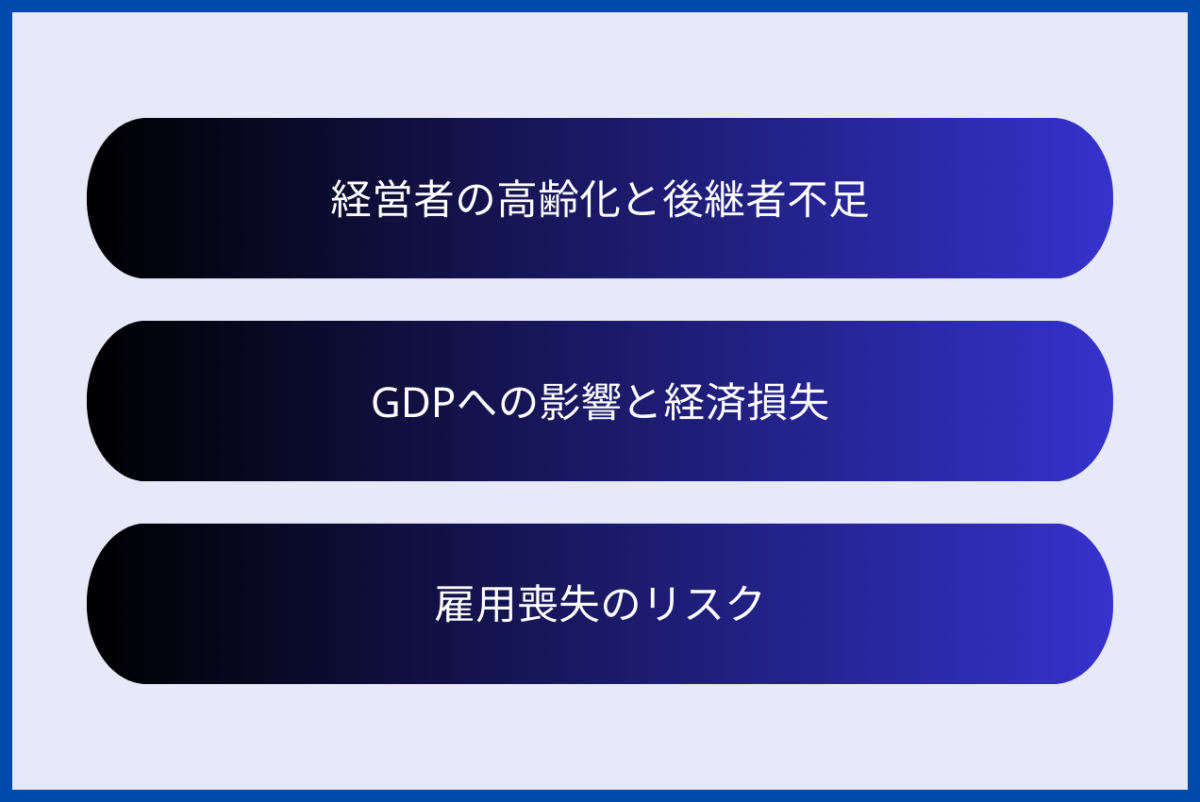
近年、中小企業経営者の平均年齢は上昇傾向にあります。2022年時点で60歳以上の経営者が全体の半数以上を占め、70歳以上の経営者も増加しています。しかし、多くの企業では後継者が決まっておらず、事業承継が進んでいません。
事業承継には、親族内で引き継ぐ「親族内承継」、従業員や役員に引き継ぐ「社内承継」、M&Aなどによる「第三者承継」などの方法があります。しかし、後継者育成の難しさや、M&Aのハードルの高さなどから、適切な承継が実現できず、経営者の高齢化に伴い廃業を余儀なくされるケースが増えています。
従業員や第三者への事業承継については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。
→従業員承継とは?メリット・デメリットや承継の流れを解説
→「第三者承継」とは?方法・メリット・事例までわかりやすく解説
経営者が70歳を超える企業のうち127万社が廃業すれば、約22兆円ものGDPが失われると推定されています。日本経済において中小企業は全企業の99.7%を占め、国内の労働人口の7割以上が中小企業で働いているため、企業の廃業は日本経済にとって大きなダメージとなります。
特に、技術力のある企業が後継者不足を理由に廃業した場合、それまで蓄積された技術やノウハウの損失は計り知れません。製造業や伝統工芸などの分野では、影響がより顕著に現れると考えられます。
事業承継がうまく進まず企業が廃業した場合、従業員の雇用も失われます。中小企業庁の予測によると、約650万人の雇用が消失する可能性があり、地域経済の衰退にも直結します。
特に地方では、大企業よりも中小企業の比率が高いため、事業承継の失敗が地域経済全体の低迷を招く可能性があります。企業がなくなることで、地元の雇用機会が減少し、若者の流出が加速することも懸念されています
事業継承を行うことで、会社や事業を次世代へ引き継ぐことができます。事業継承の種類とその現状について解説します。
親族内事業承継とは、経営者の家族が事業を引き継ぐ方法です。かつては主流でしたが、現在は減少傾向にあります。
帝国データバンクの調査によると、1980年代には60〜70%の中小企業が親族内承継を選択していましたが、2012年には約40%まで低下しました。後継者がいない、もしくは子どもに継ぐ意思がないケースが増えているため、親族内承継は今後も減少すると予測されています。
親族外事業承継とは、会社の役員や従業員、あるいは外部の関係者に経営を引き継ぐ方法です。親族内で適切な後継者が見つからない場合、従業員や外部の専門家に経営を託す選択肢が注目されています。
1980年代には30%前後だった親族外承継が、2012年には約50%まで増加しました。これは、経営の専門知識を持つ従業員や外部人材を活用し、企業の存続を図る動きが広がっているためです。
M&A(合併・買収)による事業承継とは、会社の株式や事業を他社に売却し、事業を存続させる方法です。後継者がいない場合に採用されるケースが多く、近年増加傾向にあります。
2010年と比較すると、2019年には事業承継M&Aの件数が4.4倍に増加しました。政府もM&Aを支援する制度を設けており、今後ますます活用が進むと考えられます。
2025年問題が深刻化する中、国や自治体がM&Aや事業承継を推進しているにもかかわらず、多くの中小企業では進展が見られません。背景には、経営者の意識や市場環境の課題があります。
以前は「会社を売る」ことに対する抵抗感が強かったものの、近年では認識が変わりつつあります。しかし、経営者が日々の業務に追われ、事業承継の準備に手が回らないケースが多く見られます。
また、小規模企業のM&Aでは買い手がつきにくいという課題もあります。財務状況や事業の将来性が不透明な企業は、買収リスクが高いと判断され、取引が成立しにくいのです。さらに、M&Aの手続きが複雑で、専門家の支援を受けるにも費用がかかるため、実行に踏み切れない企業も少なくありません。
こうした状況を改善するため、国や自治体はM&A支援策を強化し、より実行しやすい環境を整えています。
2025年問題を乗り越えるには、中小企業がM&Aを活用しやすい環境を整えることが不可欠です。特に、小規模事業者のM&Aを活性化することが重要になります。
そのためには、M&Aの手続きを簡素化し、短期間で成約できる仕組みを整える必要があります。例えば、M&A仲介手数料の低減や、オンラインマッチングの充実が有効な施策となるでしょう。
また、M&Aのメリットや具体的な流れを知る機会が少ないことも課題の一つです。経営者がM&Aを選択肢として検討しやすくするために、無料相談やセミナーの開催、成功事例の共有が求められます。
さらに、政府や自治体による資金支援や税制優遇措置の拡充も必要です。こうした取り組みが進めば、より多くの企業がM&Aによる事業承継を実現し、2025年問題による廃業リスクの軽減につながります。
経営者の高齢化が進む中で、多くの中小企業が事業承継の問題に直面しています。適切な対策を講じずにいると、後継者不在のまま廃業を余儀なくされる企業が増加し、日本経済に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
経営のバトンを次世代に引き継げなければ、優良な技術やノウハウが失われ、地域経済にも打撃を与える可能性があります。なぜ、多くの中小企業が事業承継に失敗するのか。その特徴について解説します。
後継者が見つからなければ、事業の継続は不可能となり、企業は廃業の道を選ばざるを得ません。特に、親族や従業員の中に適任者がいない場合、事業承継の進め方が分からず放置されてしまうケースが多く見受けられます。
近年では、M&A(合併・買収)を活用した第三者承継の選択肢もありますが、買収希望企業を見つけるためには、自社の魅力や価値を高める必要があります。経営者が適切な準備を怠ると、M&Aの相手先を見つけることができず、結局は廃業を選ばざるを得ない状況に陥ります。
かつては、経営者や従業員が高齢になった際、若手社員が技術や経営ノウハウを引き継ぎ、事業を存続させることが一般的でした。しかし、現在の日本では少子高齢化が進行し、若い世代の人材確保が困難となっています。結果、経営者や主要な従業員の引退後に適任者が見つからず、廃業を余儀なくされる企業が増えています。
人材不足は、2025年問題の主要な課題の一つです。特に地方では、若年層の流出が激しく、後継者どころか従業員すら確保できない状況が深刻化しています。
2025年問題への対策とその注意すべき点について解説します。
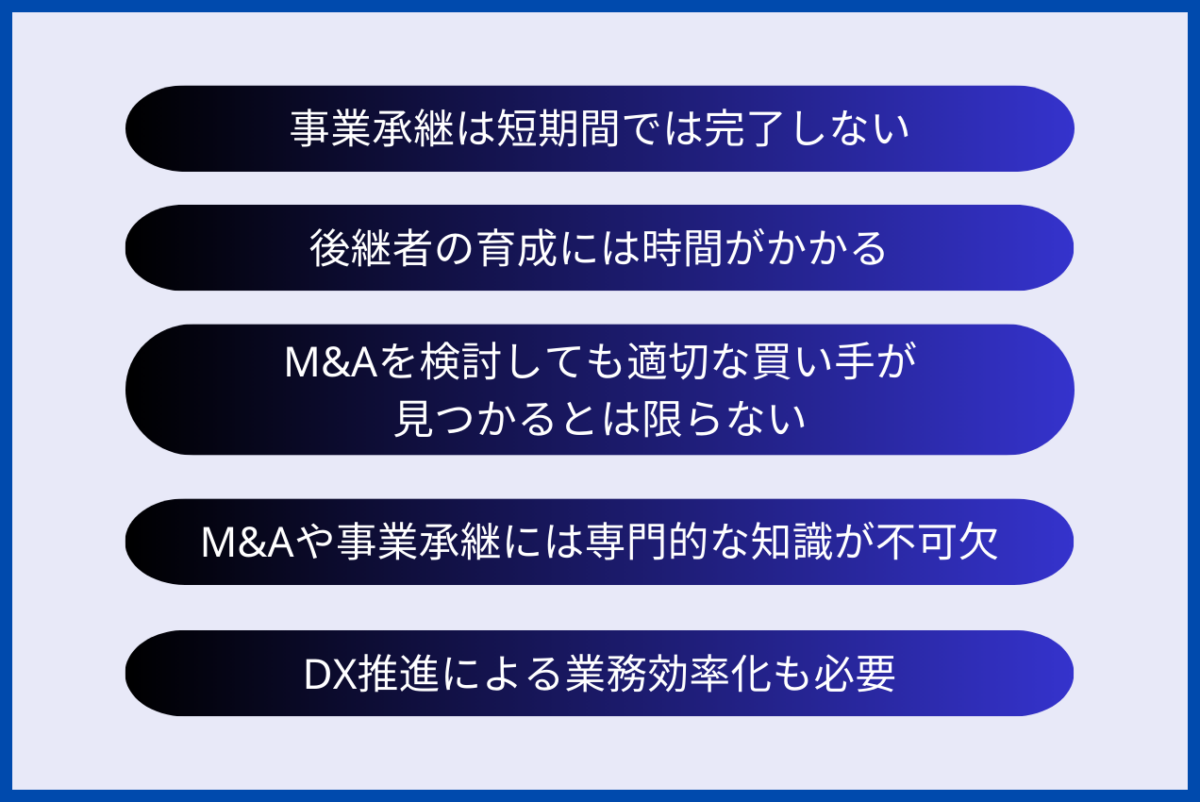
事業承継を成功させるためには、長期的な計画が不可欠です。まず、後継者を見つけることが第一歩となりますが、経営能力を備えた適任者を確保することは容易ではありません。
親族内承継や社内昇格による承継が難しい場合、M&Aによる第三者承継も選択肢となります。中小企業庁では「事業引継ぎ支援センター」を設置し、全国的にM&Aのマッチング支援を行っています。しかし、M&Aの実施には、相手企業の選定、交渉、契約締結などのプロセスを踏む必要があり、計画的に進めなければスムーズな承継は難しくなります。
仮に後継者が決まっていたとしても、経営を任せられるレベルに育成するには長い時間を要します。
後継者は、経営スキルの習得だけでなく、従業員・取引先との信頼関係の構築やリーダーシップの確立が求められます。現経営者のノウハウを引き継ぎながら、業務の経験を積み、徐々に経営の実務を担っていくプロセスが必要です。
こうした育成期間を確保するためにも、事業承継の準備はできるだけ早く始めることが重要です。
後継者が不在の場合、M&Aによる事業承継は有効な選択肢となります。しかし、M&Aを希望しても、必ずしも理想的な買収先が見つかるわけではありません。
買収を検討する企業は、事業の成長性やシナジー効果を重視するため、収益性の低い企業や独自の強みがない企業は買収の対象になりにくい傾向があります。そのため、M&Aによる承継を成功させるためには、企業の魅力を高める経営改善が必要です。
シナジー効果については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。
→シナジーとは?ビジネスでの意味・効果生み出す方法・M&A事例を解説
M&Aを通じた事業承継を進める場合、相手企業の選定から契約締結までのプロセスにおいて、法律・財務・税務といった専門知識が必要になります。特に、契約条件の交渉やデューデリジェンス(企業価値評価)は慎重に進めなければなりません。
このような手続きをスムーズに進めるためには、専門家のサポートを受けることが重要です。M&A仲介会社や事業承継コンサルタントを活用し、適切なアドバイスを受けながら計画的に進めることで、より良い結果を得られるでしょう。
デューデリジェンスやM&A仲介会社については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。
→DD(デューデリジェンス)とは?目的・M&Aの際の流れ・費用を解説
→【徹底比較】M&A仲介会社・マッチングサイト一覧!大手5社はどこ?
事業承継だけでなく、2025年問題においては労働力不足への対応も不可欠です。企業の存続を確保するためには、デジタルトランスフォーメーション(DX)を進め、業務の効率化を図ることが求められます。
特に、中小企業ではアナログな業務プロセスが多く残っているため、デジタルツールの活用により労働生産性を向上させることが重要です。具体的には、クラウド会計システムやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入を進めることで、業務の負担を軽減できます。
事業承継問題や2025年問題で廃業を選択した企業には、黒字経営にもかかわらず廃業した企業や譲渡先をみつけることができず廃業した企業もあり、事業承継できずに廃業した中小企業の事例を紹介します。
明治時代から彦根城内で営業していた料理旅館「八景亭」は、長年にわたり地元住民や観光客に愛されていました。
しかし、経営者が病気で倒れたことで経営が困難となり、2017年に約130年の歴史に幕を閉じました。後継者を探していたものの見つからず、さらに江戸時代から続く建物の老朽化が進んでいたことも廃業の決定に影響を与えました。
東京都墨田区にあった岡野工業は、高い技術力を誇る金属加工会社でした。リチウムイオン電池ケースや痛みの少ない注射針「ナノパス33」などを開発し、大手企業やNASAにも製品を提供するなど、世界的な評価を得ていました。
しかし、経営者の2人の娘は事業を継ぐ意思がなく、後継者の確保ができませんでした。結果として、2020年に黒字経営ながらも廃業を選択せざるを得ませんでした。
1868年創業の木挽町辨松は、歌舞伎座前に本店を構え、観劇客や役者に愛される弁当屋でした。一時は渋谷や六本木などにも店舗を展開し、繁盛していました。
しかし、2020年に後継者不在に加え、店舗移転の投資負担や設備の老朽化が重なり、事業継続が困難となりました。譲渡先を探していたものの、新型コロナウイルスの影響で交渉が難航し、最終的に廃業を選ぶことになりました。
2018年、沖縄県宮古島市平良狩俣にあった琉球泡盛の酒造所「千代泉酒造所」が廃業しました。経営者が2013年に亡くなったことをきっかけに、事業を継ぐ後継者が見つからず、休業状態が続いた後、正式に廃業に至りました。
経営者の親族や宮古島内の他の酒造所など、承継先を探していたものの、引き継ぐ意志を持つ企業や個人は現れず、戦後間もなくから泡盛の製造を続け、地元住民に愛されてきた千代泉酒造所でしたが、現在では市場から姿を消し、幻の泡盛となっています。 会社売却や事業承継など、M&Aに関するお悩みは、ぜひM&A Leadへご相談ください。 当社は「完全成功報酬制」を採用しており、譲渡が成立し譲渡対価が入金されるまでは一切料金をいただきません。お気軽にご相談いただけます。 また、知識・支援実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、ご相談からクロージングまで、売主様に徹底的に寄り添いサポートいたします。 さらに、当社のアドバイザーだけでなく、当社が運営するM&Aアドバイザー紹介プラットフォームにご登録いただいているM&Aアドバイザー様のネットワークも活用可能なので、どのような業界・業種の案件にもご対応可能です。 当社はこの強みをフルに活用して、M&Aをお考えのオーナー様に徹底的に寄り添い、売却成功までサポートいたします。 無料相談は随時お受けしておりますので、お電話・Webよりお気軽にお問い合わせください。
本記事では、2025年問題と事業承継の課題について解説しました。2025年には、多くの中小企業経営者が高齢化し、約127万社の企業が後継者不在の問題に直面すると予測されています。このままでは、地域経済や日本全体の産業基盤に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
事業承継をスムーズに進めるためには、財務状況の整理や経営の見える化を行い、企業の価値を明確にすることが重要です。国や自治体の支援制度も活用しながら、自社にとって最適な方法を検討しましょう。
2025年問題は、多くの中小企業にとって避けては通れない課題です。事業承継を成功させるためには、経営者自身が危機意識を持ち、早い段階から準備を進めることが求められます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
M&A・事業承継のご相談はお任せください。 経験豊富なM&Aアドバイザーが、無料でお話をお伺いし、M&Aに捉われず、ご相談いただきました会社・事業オーナー様に最適なご提案させていただきます。 まずはお気軽にお問い合わせください。
POPULAR