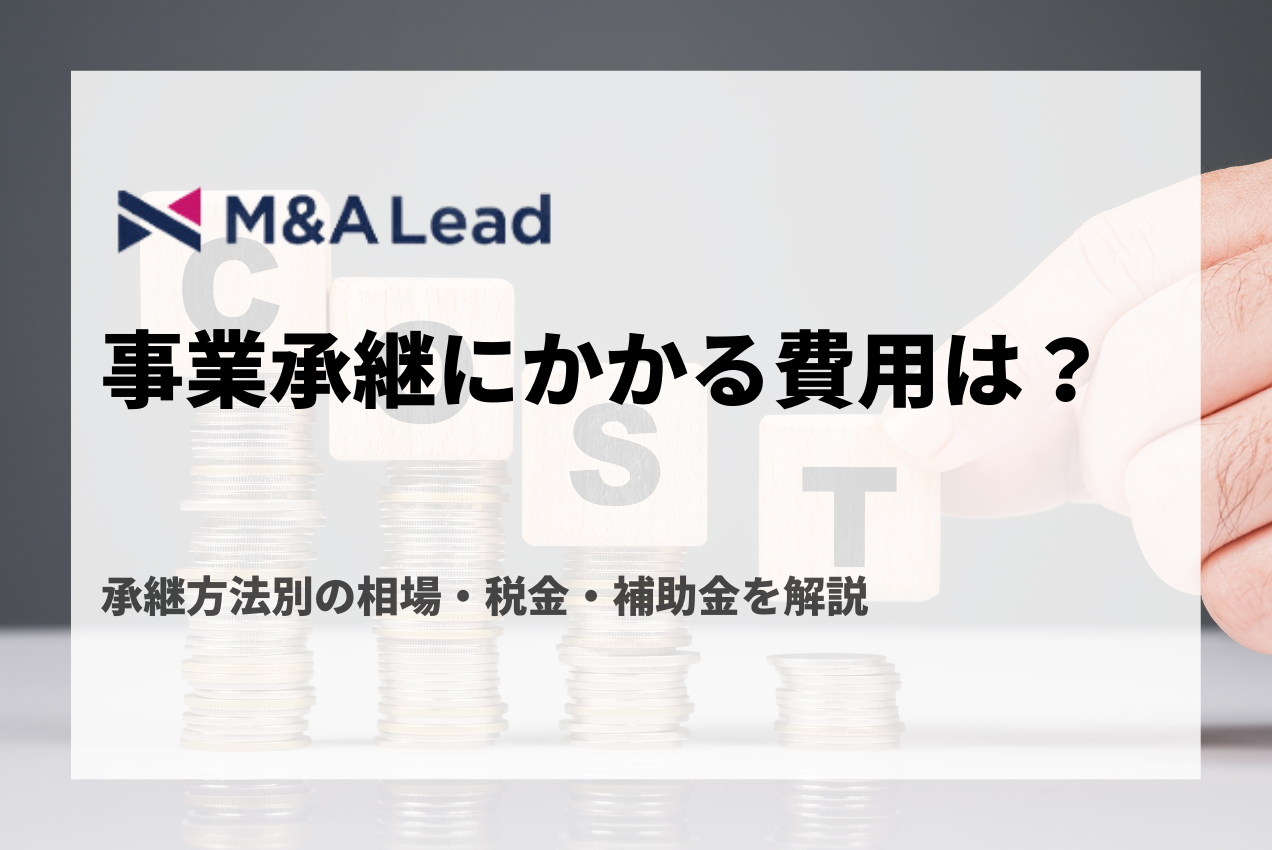
事業承継は、経営者にとって大きな節目ですが、「一体いくらかかるのか分からない」という不安の声も多く聞かれます。実際のところ、事業の引き継ぎには税金や専門家への報酬など、さまざまな費用が発生します。しかし、事前に費用の内訳や相場を理解しておくことで、過剰な出費を避けることができ、スムーズな承継が可能になります。
この記事では、事業承継にかかる主な費用の種類や相場、税金のポイント、補助金制度の活用法までを分かりやすく解説します。
この記事の監修者事業を次の世代へと引き継ぐ場面では、目に見えるコストだけでなく、想定外の出費が発生することも少なくありません。「どのくらいお金がかかるのか」「何に費用が必要なのか」を事前に知っておくことは、円滑な承継の第一歩です。
実際、事業承継では相続税・贈与税といった税負担に加えて、登記や名義変更のための手数料、法的・税務的なアドバイスを受けるための専門家報酬が必要です。事業規模や承継の方法によって異なるため、まずは全体像を把握することが重要です。
ここでは、事業承継で発生する代表的な費用とその背景について、基本から丁寧に解説します。
事業承継は、単に代表者の肩書きを引き継ぐだけでは終わりません。株式や資産の移転、契約関係の見直し、相続や贈与に関する手続きなど、法務・税務・財務のさまざまな分野にまたがる作業が必要です。適切に行うには、弁護士や税理士などの専門家の協力が不可欠であり、その分の報酬が発生します。
また、株式や不動産を承継する場合には、相続税や贈与税、不動産取得税、登録免許税といった税金も発生します。これらの費用は、事業の規模や資産内容、承継方法によって大きく変わるため、事前に全体像を把握しておくことが重要です。
事業承継に関わるコストは、大きく以下のように分類されます。
第一に、税金関連の費用があります。相続や贈与を通じて株式や不動産を移転する場合、相続税や贈与税が課税されます。また、不動産の移転には登録免許税や不動産取得税がかかるケースもあります。
次に、専門家への報酬です。税務や法務の手続きは複雑なため、多くの経営者は税理士・会計士・弁護士などに依頼しています。M&Aによる承継を検討する場合には、M&A仲介会社やアドバイザーの力を借りることが一般的です。
最後に、手続きに関する実費が挙げられます。会社登記の変更、契約書の作成、資産の名義変更などにかかる手数料や印紙代などです。
承継の方法や事業の状況に応じて、これらの費用の内容や金額が変わるため、次章では具体的なケースごとの違いを見ていきます。
会社売却や事業承継など、M&Aに関するお悩みは、ぜひM&A Leadへご相談ください。
当社は「完全成功報酬制」を採用しており、譲渡が成立し譲渡対価が入金されるまでは一切料金をいただきません。お気軽にご相談いただけます。
また、知識・支援実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、ご相談からクロージングまで、売主様に徹底的に寄り添いサポートいたします。
さらに、当社のアドバイザーだけでなく、当社が運営するM&Aアドバイザー紹介プラットフォームにご登録いただいているM&Aアドバイザー様のネットワークも活用可能なので、どのような業界・業種の案件にもご対応可能です。
当社はこの強みをフルに活用して、M&Aをお考えのオーナー様に徹底的に寄り添い、売却成功までサポートいたします。
無料相談は随時お受けしておりますので、お電話・Webよりお気軽にお問い合わせください。
事業承継にかかる費用は、「誰に引き継ぐか」によって大きく変わります。親族に託すのか、従業員に譲るのか、それともM&Aで第三者に引き継ぐのか。それぞれの方法で発生するコストや手続きはまったく異なります。
親族承継であれば税務上の特例制度が活用できる可能性がある一方、M&Aによる承継では専門家への報酬が高額になるケースもあります。また、従業員承継では後継者の資金調達の有無によっても必要な費用が大きく変わります。
ここでは3つの主要な承継パターン別に、実際にどのような費用がかかるのか、その特徴と注意点を分かりやすく解説していきます。
 に発生する費用の違いを承継パターンごとまとめた図解になります。具体的には、親族に承継する場合、社員(従業員)に引き継ぐ場合、M&Aで第三者に譲渡する場合となります。
に発生する費用の違いを承継パターンごとまとめた図解になります。具体的には、親族に承継する場合、社員(従業員)に引き継ぐ場合、M&Aで第三者に譲渡する場合となります。
親族間での承継は伝統的な方法であり、経営者の子どもや兄弟姉妹などが後継者となるケースが一般的です。
親族に承継する場合の費用は比較的抑えられる傾向がありますが、一定のコストは発生します。会社の株式や不動産などを無償で譲渡する場合、贈与税や相続税の負担が生じる可能性があります。事前に生前贈与を行うか、相続時精算課税制度を利用するかなど、状況に応じた税務戦略が必要です。
また、専門家による資産評価や税額の試算も必要になるため、税理士や会計士への依頼料が発生します。承継がスムーズに行えれば、必要経費は限定的ですが、相続人間のトラブルや遺留分の問題が発生すると、弁護士のサポートが必要となり、追加の費用がかかることもあります。
親族以外の役員や従業員に経営を託すケースでは、資産の取得に対する贈与税や株式の買い取りに必要な資金調達など、資金面での課題が発生しやすいのが特徴です。
後継者が個人で株式を買い取る余裕がない場合、金融機関からの借入や、承継支援制度を活用することも選択肢となります。また、従業員が承継することで、一定の継続性や社内理解を得やすい一方で、経営責任や資金管理の体制づくりには時間がかかることもあります。
役員や従業員による承継の場合も、専門家の助言が不可欠であり、税理士やM&Aアドバイザーへの相談費用や手続き代行料が必要になります。親族内承継に比べて、外部の支援が増える分、全体的な費用は高くなりやすいといえます。
M&Aを通じて第三者企業に承継する方法は、近年中小企業でも増加傾向にあり、M&A仲介会社やマッチングサービスを活用して買い手を探すのが一般的です。
費用面で特徴的なのは、M&Aアドバイザーへの報酬体系です。一般的には、相談料・着手金・中間金・成功報酬といった形で分割されることが多く、成功報酬は「レーマン方式」と呼ばれる売却金額に応じたパーセンテージで計算されます。
中には「完全成功報酬型」を謳う仲介会社もありますが、手数料の総額は承継金額の5〜10%に及ぶこともあり、3つの承継方法の中で最も費用負担が大きくなる傾向があります。
ただし、企業価値が高ければ高額売却が可能なため、費用以上のリターンを得られる可能性もあるのがM&Aのメリットです。
事業を次世代に引き継ぐ際、避けて通れないのが税金の問題です。承継の方法や内容によって、負担すべき税金の種類と金額は大きく変わります。想定していなかった税負担が発生することで、承継そのものが困難になるケースもあります。
特に注意すべきなのは、相続税や贈与税などの資産移転に関する税金です。加えて、法人税や消費税、登録免許税、不動産取得税といった税金も、ケースによっては無視できない金額になります。
以下で事業承継の際に発生する税金について、それぞれ解説します。

事業承継において相続税は、特に大きな負担となる可能性がある税金です。経営者が亡くなり、後継者が株式や不動産などの資産を相続する場合、資産価値に応じて相続税が課されます。問題は、評価額が高額である一方、現金が手元にないケースが多く、納税資金の確保が困難になるリスクがあるという点です。
相続税は、取得する資産の金額が多くなるほど税率が上がる累進課税制度が採用されており、税率は10%〜55%と幅があります。会社の株式の評価額が5,000万円であった場合、その相続税は数百万円単位になることも珍しくありません。
しかし、一定の控除制度や特例を活用することで、税負担を大きく軽減することが可能です。配偶者控除を使えば、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までは課税されません。生命保険の非課税枠や、後述する相続時精算課税制度・事業承継税制といった制度を活用することで、資金繰りに大きな差が出てきます。
| 法定相続分による取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下の場合 | 10% | ₋ |
| 3,000万円以下の場合 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下の場合 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下の場合 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下の場合 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下の場合 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下の場合 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超の場合 | 55% | 7,200万円 |
相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母が20歳以上の子や孫に資産を贈与する場合に適用される制度で、累計2,500万円までの贈与について贈与税がかからないというメリットがあります。
通常、贈与には年間110万円までの非課税枠がありますが、超えた分には累進課税が適用されます。この制度を選択すれば、年間の贈与額に関係なく2,500万円までは非課税とされ、超過分については一律20%の贈与税が課されます。そして、贈与者が亡くなった際に相続税を精算する仕組みとなっています。
制度の特徴は、生前のうちにまとまった資産移転が可能になる点です。事業承継の現場では、早い段階から株式を後継者に移転させ、経営の引き継ぎを計画的に進めたいというニーズにマッチしています。
ただし、いったん相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与には以後この制度しか使えなくなるため、慎重な検討が必要です。
相続税の現金納付が難しい中小企業のために設けられているのが、事業承継税制による納税猶予制度です。制度を活用すると、後継者が引き継ぐ非上場株式にかかる相続税や贈与税の最大100%が猶予されるため、事業の継続に大きな安心材料となります。
納税猶予の対象株式数や割合に上限がありましたが、2018年の税制改正によって、特例措置として全株式に対する猶予が認められるようになり、猶予割合も80%から100%へと拡大されました。これにより、後継者が納税のために事業用資産を手放す必要がなくなり、事業の安定的な継続が可能になります。
ただし、事業承継税制の特例措置は永続的なものではなく、2027年12月31日までの期間限定の特例措置です。適用を受けるためには、2026年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出しておく必要があるなど、利用には明確な期限と条件があります。
相続税対策としては非常に有効な制度である一方、申請のタイミングや条件を逃すと適用されないというリスクもあるため、事前に税理士などの専門家に相談することが不可欠です。
事業承継で生前に株式や資産を移転する場合、贈与税が課されることがあります。贈与税の基本制度は「暦年課税」で、1月から12月までの1年間に受け取った財産のうち、基礎控除額(110万円)を超える部分に対して課税されます。税率は贈与額に応じて10%~55%の累進課税です。
贈与税には2種類あり、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に分けられます。特例贈与財産とは、18歳以上の受贈者が、60歳以上の直系尊属(親や祖父母など)から贈与を受けた場合に適用され、より有利な税率が設定されています。事業承継で親子間の贈与を検討する際には、この特例の有無も確認しておくべきポイントです。
贈与税の負担を抑える方法として、「相続時精算課税制度」の利用があります。これは、2,500万円までの贈与が非課税となり、超過分には20%の一律課税がされ、最終的には相続時に精算される仕組みです。
さらに、一定の条件を満たすことで贈与税の納税が猶予される「事業承継税制」も利用可能です。改正により、かつては1対1に限定されていた贈与者・受贈者の組み合わせも、複数人での贈与に対応可能となりました。
制度には事前の計画提出や事業継続などの要件があるため、制度活用には専門家との連携が不可欠です。
| 一般贈与財産 | 特例贈与財産 | ||
| 課税価格 | 税額 | 課税価格 | 税額 |
| 200万円以下の場合 | 10% | 200万円以下 | B×10% |
| 300万円以下の場合 | 15%-10万円 | 400万円以下 | 15%-10万円 |
| 400万円以下の場合 | 20%-25万円 | 600万円以下 | 20%-30万円 |
| 600万円以下の場合 | 30%-65万円 | 1,000万円以下 | 30%-90万円 |
| 1,000万円以下の場合 | 40%-125万円 | 1,500万円以下 | 40%-190万円 |
| 1,500万円以下の場合 | 45%-175万円 | 3,000万円以下 | 45%-265万円 |
| 3,000万円以下の場合 | 50%-250万円 | 4,500万円以下 | 50%-415万円 |
| 3,000万円超の場合 | 55%-400万円 | 4,500万円超 | 55%-640万円 |
法人税は、企業が得た利益に対して課される税金です。通常の相続や贈与による事業承継では法人税は発生しませんが、事業譲渡という形をとる場合には法人税が課されることがあります。
たとえば、事業を第三者に譲渡して対価を受け取るM&Aでは、法人が譲渡益を得るため、それが課税対象となります。中小企業の場合、800万円以下の所得に対しては15%の軽減税率が適用され、それ以上は23.2%の税率となります。
法人税は、会社の利益が出て初めて発生する税金であるため、事業承継後の再編や売却時の税務戦略として意識すべきポイントです。
消費税は、モノやサービスを提供・購入したときに発生する税金です。事業承継においては、承継の形式によって消費税が発生するかどうかが分かれます。
たとえば、株式譲渡による事業承継は「資本取引」とみなされるため、消費税の課税対象とはなりません。しかし、事業譲渡の形式をとる場合、個別の資産(在庫・設備・営業権など)ごとに取引が行われることになり、一部の資産については消費税の課税対象になることがあります。
そのため、どの承継スキームを選択するかによって、消費税の取り扱いにも違いが出てくる点は注意が必要です。
登録免許税は、法人登記や不動産登記など、法律上の登録手続きを行う際に必要な税金です。事業承継では、後継者による会社の代表者変更や、不動産の所有権移転登記などが必要となるため、登録免許税が発生します。
たとえば、会社の合併登記では0.4%、会社分割では2%の税率が基本となりますが、事業承継税制の特例を利用すれば、合併時は0.2%、分割時は0.4%まで軽減される措置が用意されています。
このように、税制優遇措置を活用すれば、登記関連のコストも抑えることができます。ただし、減免を受けるには特例承継計画の提出など、一定の手続きを事前に済ませておく必要があります。
不動産取得税は、不動産を取得した際に課される地方税です。相続による取得には課税されませんが、贈与や譲渡によって取得した場合には課税対象となります。
税率は原則として以下のとおりです。
土地・住宅:3%
住宅以外の家屋:4%
ただし、事業承継税制の対象となるケースでは、土地・建物:2.5%、非住宅家屋:3.3%と軽減される場合があります。登録免許税と同様に、軽減措置を受けるには計画的な準備と手続きが必要です。
不動産が絡む事業承継では、取得税だけで数十万円から数百万円の負担になるケースもあるため、制度の活用は非常に重要です。
事業承継を専門家に依頼する際は、サポートの内容や難易度に応じてさまざまな費用が発生します。初期相談は無料のケースもありますが、本格的な支援を受けるには、相談料・着手金・報酬金・成功報酬など、段階的なコストが必要になるのが一般的です。
弁護士に事業承継を依頼した場合、主に発生する費用は「相談料」「着手金」「成功報酬」「実費」の4つに分類されます。
相談料:1時間あたり5,000円〜1万円が相場。初回無料の事務所もあります。
着手金:正式な依頼を受けた段階で発生し、50万円〜100万円前後が目安です。
成功報酬:依頼された案件が完了した際に支払う報酬で、承継により得られた利益の10%前後が基準となります。
実費:交通費、登記費用、収入印紙代など。案件によって変動します。
弁護士は、株式の譲渡契約や遺産分割協議書の作成、相続トラブルの防止や対応に長けており、法的なリスクを回避しながら承継を進める上で重要な存在です。その分、費用は高めですが、トラブル予防・紛争回避の効果は非常に大きいといえます。
税理士や会計士は、税金や財務の視点から事業承継を支援します。依頼する業務の範囲によって報酬は大きく異なりますが、主な費用項目は以下のとおりです。
自社株評価・相続税評価額の算出:10万円〜50万円前後
税務申告(相続税・贈与税):30万円〜100万円前後
事業承継計画・組織再編計画の策定:100万円〜300万円程度
事業承継税制の適用サポート:50万円〜200万円程度
また、複数の業務を一括して依頼する「包括支援プラン」などを設けている事務所もあり、トータルで300〜500万円前後の費用がかかるケースも珍しくありません。
税理士や会計士は、事業承継における税負担を最小限に抑えるために不可欠な存在であり、特に相続税や贈与税の節税策を立てる上で非常に重要です。
M&Aによる事業承継を進める場合、多くの企業がM&Aアドバイザーや仲介会社にサポートを依頼します。費用体系は会社によって異なりますが、主に以下のような報酬項目があります。
相談料・着手金:0円〜100万円(無料のケースも多数)
中間報酬:基本合意成立時に発生。100万円〜300万円程度
成功報酬:売却価格に対する一定割合で、レーマン方式(取引額に対する料率)が一般的です(例:1億円の取引で500万円程度)
最近では、完全成功報酬型(クロージングまで費用ゼロ)を採用する仲介会社も増えており、初期費用を抑えてM&Aに取り組みやすい環境が整ってきています。
M&Aアドバイザーは、買い手企業の選定・企業価値評価・交渉・契約手続きまでを一括支援してくれる存在であり、第三者承継を成功させる上で極めて重要な役割を担います。
事業承継には多額の費用がかかる可能性がありますが、すべてを自社でまかなう必要はありません。実は、国や自治体が用意する補助金・融資・税制優遇をうまく活用すれば、費用負担を大幅に軽減することが可能です。
こうした支援制度は、中小企業の廃業を防ぎ、経済を活性化させることを目的に整備されており、後継者不在や資金不足に悩む企業にとって強力な味方になります。
「事業承継・引継ぎ補助金」は、中小企業が事業の引継ぎを機に新たな取り組みを始めたり、経営革新を行ったりする場合に、その費用の一部を補助する制度です。補助の対象には、親族内承継・従業員承継・M&Aによる承継のすべてが含まれます。
補助金には下記のいくつかの枠があります。
経営者交代枠(経営革新などの実施)
専門家活用枠(仲介手数料や契約書作成費用など)
廃業・再チャレンジ枠(事業の整理・清算に伴う費用)
以上が設けられており、それぞれに応じた支援を受けることが可能です。補助率は最大で対象経費の3分の2、補助上限額は1,200万円程度が一般的な相場となっています。ただし、採択には一定の審査があり、承継後の経営革新や地域貢献といった具体的な取り組みが求められるため、事前準備が不可欠です。
補助金の公募は年に数回行われるため、最新のスケジュールや条件を中小企業庁や支援センターの公式サイトで確認しておくことをおすすめします。
補助金に加えて、融資制度も費用負担の軽減に役立ちます。なかでも、日本政策金融公庫では、中小企業の事業承継に特化した各種融資メニューを用意しています。
代表的な制度には以下のようなものがあります
事業承継・集約・活性化支援資金:後継者が事業を引き継ぎ、再構築や成長を目指す企業向けの融資。最大7億2,000万円まで対応可能。
女性・若者/シニア起業家支援資金: 承継時の起業・独立を目指す後継者(女性・35歳以下・55歳以上)向けの制度。起業からおおむね7年以内であれば、最大7億2,000万円の融資枠が活用可能です。
再建資金・事業再生支援資金: 経営が厳しい企業の再起支援を目的とした融資制度。返済期間が最大20年、うち2年は据え置き可能など、返済条件に余裕があるのが特徴です。
これらの融資制度は、承継直後の資金繰り不安や、M&Aにかかる一時的なコスト負担を和らげるための強力な支援となります。
事業承継にかかるコストの中でも特に重くのしかかるのが、相続税・贈与税の負担です。この税負担を大きく軽減できるのが、国の「事業承継税制」です。
この制度は、一定の条件を満たすことで、後継者が引き継ぐ非上場株式にかかる相続税や贈与税の100%が猶予されるというもので、現在は2027年末までの時限措置として運用されています。
猶予を受けるためには、以下のような要件を満たす必要があります
・特例承継計画を2026年3月末までに都道府県に提出
・後継者が5年間継続して代表を務める
・雇用維持などの基準を満たすこと
さらに、法人向けだけでなく、個人事業主を対象とした個人版事業承継税制も用意されており、一定の資産に対する相続税・贈与税が全額猶予される仕組みです。
適用には手続きや条件が多いため、税理士などの専門家に相談のうえ計画的に進めることが重要です。
会社売却や事業承継など、M&Aに関するお悩みは、ぜひM&A Leadへご相談ください。
当社は「完全成功報酬制」を採用しており、譲渡が成立し譲渡対価が入金されるまでは一切料金をいただきません。お気軽にご相談いただけます。
また、知識・支援実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、ご相談からクロージングまで、売主様に徹底的に寄り添いサポートいたします。
さらに、当社のアドバイザーだけでなく、当社が運営するM&Aアドバイザー紹介プラットフォームにご登録いただいているM&Aアドバイザー様のネットワークも活用可能なので、どのような業界・業種の案件にもご対応可能です。
当社はこの強みをフルに活用して、M&Aをお考えのオーナー様に徹底的に寄り添い、売却成功までサポートいたします。
無料相談は随時お受けしておりますので、お電話・Webよりお気軽にお問い合わせください。
事業承継は、経営者にとって大きな節目であり、同時に多くのコストが発生する重大なプロセスです。税金、専門家への報酬、手続き関連費用など、目に見える支出はもちろん、事前の準備や情報収集にも時間と費用がかかります。
しかし、こうした費用は「必要な投資」であると同時に、制度や補助金を活用することで十分に軽減することが可能です。
たとえば、事業承継税制での納税猶予、補助金による費用補填、公的融資による資金繰りの安定化など、あらゆる角度からコストを抑える方法が用意されています。
最も大切なのは、「早めの準備と相談」です。専門家や公的支援機関に早期から相談し、適切な制度を選び、無理のない形で事業を引き継ぐ体制を整えることで、事業承継を“未来への投資”へと変えることができます。
承継を迷っている経営者や、これから準備を進めたいと考えている後継者の方は、まずは身近な支援機関や専門家に話を聞くことから始めてみてください。
M&A・事業承継のご相談はお任せください。 経験豊富なM&Aアドバイザーが、無料でお話をお伺いし、M&Aに捉われず、ご相談いただきました会社・事業オーナー様に最適なご提案させていただきます。 まずはお気軽にお問い合わせください。
POPULAR